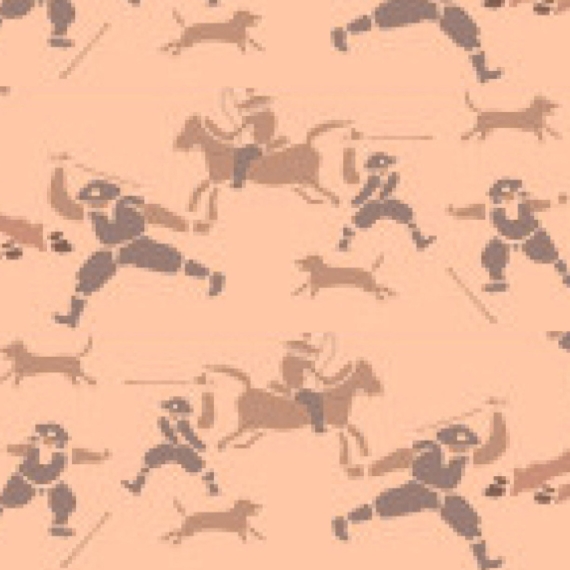物語
Old Tale
#1109
読経地蔵(大泉寺)
ソース場所:甲府市古府中町5015 大泉寺
●ソース元 :・ 裏見寒話 附録 山河・社閣・古跡 の項より
甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 (参照 2024-05-24)
●画像撮影 : 2015年11月10日
●データ公開 : 2016年06月24日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。












[概 要] 昔、大泉寺境内のお地蔵さんが、「夜になると唇を動かし読経する」という噂がたった。この噂に多くの人々が集まったが、名僧で知られる百尾和尚は、「石地蔵を拝むのは良いが、まちがった信仰はいけない。読経に聞こえたのは虫の音かもしれない。」と謎を解き、百尾和尚への信頼はますます深まった。そして、お地蔵さんは読経地蔵と呼ばれるようになったと云う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
誦経地蔵
大泉寺の墓地にある石地蔵が夜な夜な読経すると云う噂が府下に鳴り響いた。お婆さんたちは。これを聞いて恐がり参詣を避けた。
時は、盛夏の頃、夜中もこの噂を聞いた人々が墓地におおぜいおとずれた。
そこで 百尾和尚が、その人達に向かい「今年の夏は木々がとても繁茂している。蜂やアブなどが木に巣を作り、その鳴声がするのではないだろうか?昼間は世の中の物音に紛れて聞こえないのが、夜になり、四方が静かになるので、その鳴声が読経のように聞こえるのではないだろうか?何で、石像が唇を動かし声を出して誦経するものか? そうは言え、読経に聞こえると云えば聞こえ、虫の声と聞こえれば聞こえる。 この石像を本堂の前に持って行き、それでも読経するようなら地蔵が妖を成していると云う事だ。 そんな事はあるまい。」と本堂の前に出すと、たちまち誦経が止んだ。やはり蜂や虻が寄って鳴いていただけでした。
裏見寒話 附録 山河・社閣・古跡 の項より・・・「甲斐志料集成」3 p265-266
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。