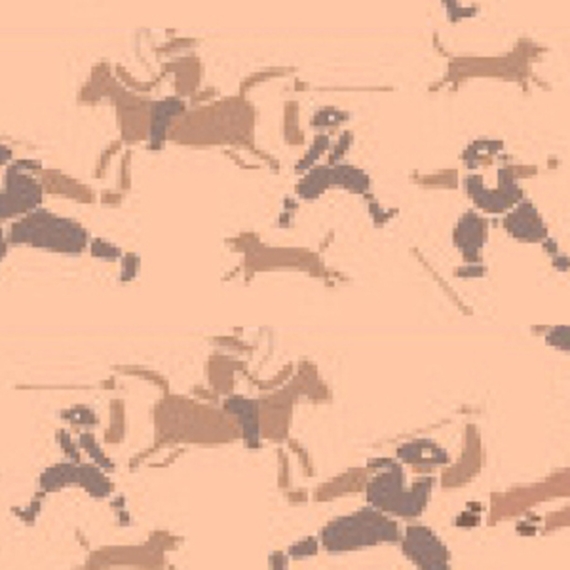物語
Old Tale
#1245
明見のいわれ
ソース場所:富士吉田市小明見
●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2017年10月24日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
近いにもかかわらず「富士山を見ることの出来ない地」、富士山の写真でイメージして下さい。












[概要] 富士山麓にも関わらず、富士山の見えない地域がある。背戸山に隠れて富士山の姿が見えない。富士山が現れた時、凄まじい音や振動に近くの村々では村人が不安に右往左往していたのに、「外に出てみろ!」と心配する人の声も聞かず「夜は寝るものだ、明日見るから」と家から出なかった翌朝、外に出てみると、、、。 アマノジャクの作った明見湖は蓮の花が美しい湖です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
明見のいわれ
アメノヌボコを使ってどろどろにとけた土をかため、イザナギの命があらかたの国造りをしたあと、山や谷を造ったり湖や川筋をこしらえたりの仕上げの仕事は天(あま)つ神、地(くに)つ神がそれぞれ分担で受持っていた。
富士山造りはアマノジャクが監督で大男のデイラボッチがやるようにとの命令が日本中全ての山造りの神々を支配する大山祇命(おおやまずみのみこと)から出された。
デイラボッチが富士山を作りはじめると、大またで歩く「どしんどしん」という足音で人々は目をさました。大男のデイラボッチは暑いのがきらいで夜しか働かなかったのである。
月あかりでよくはわからぬが黒くて天まで届くかと思われるような大男が天坪棒をかついでモッコを吊し、大またにのっしのっしと歩くさまがよく見えた。村人たちがおどろきおそれ、右往左往するのもむりはない。
村人のうろたえるのも何のその、かついできたモッコの土をあけてはまた本栖村や精進村へ行って土をほり、またやって来ては同じところに土をあけるので、あれよあれよという間に土が山と重ねられていった。
ところが、どこの村も大騒ぎだというのに小明見村には、妙に度胸の座った、悪くいうとひねくれものの名主がいた。この名主デイラボッチの地ひびきたてる足音にも村人達がアレヨアレヨと騒ぐ声にも全く気付かぬふりをして、一歩も家を出ょうともしなかった。
丑三つどきもすぎる頃には山は次第に高くなり、みたこともない大きな大きな、そして美しい山の形が月明かりの中にくっきりと輪郭を描いていた。
村人は恐怖の中にも美しい山の出現に畏敬し、いっこうに出て来ようともしない名主に知らせに走った。
「名主さん、とてつもない、えらいそりゃあみごとな大きな山が一ぺんにできて、みんなびっくりどうだね、見てもらえないかね」と村人が言ったが
「何を言ってるか、いちいちそんなことに気をとられてろくに寝ないでいたじゃ明日一日働けるか、夜は寝るものだ、だいいちなくなるもんでもあるまいし、明日見る方が余程良く見えるというものだ。さあさあ帰ってねろ。明日見ろ明日見ろ」と大声でどなると戸を閉めて寝てしまった。
これを聞いて怒ったのが、デイラボッチをかんとくしていた天と地の間に割ってはいり、天を持ち上げたという大力のアマノジャクであった。
アマノジャクは「よしこの村からは美しい山を見えなくしてやれ」と、土をすくって村の境に盛り上げた。二すくいめをとろうとしたら明かるくなって来たのでそうそうにやめた。夜があけてみると、小明見村では村半分ほどが富士山が見えない土地になっており、いままでなかった湖水ができていた。背戸山と明見湖がそれである。
内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。