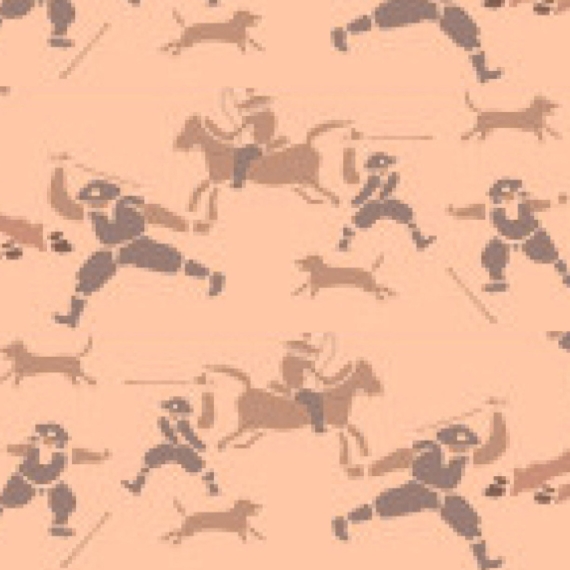物語
Old Tale
#1173
原山さんのうなぎの放流
ソース場所:甲府市美咲1-187 原山神社
●ソース元 :・ 山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2017年01月05日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
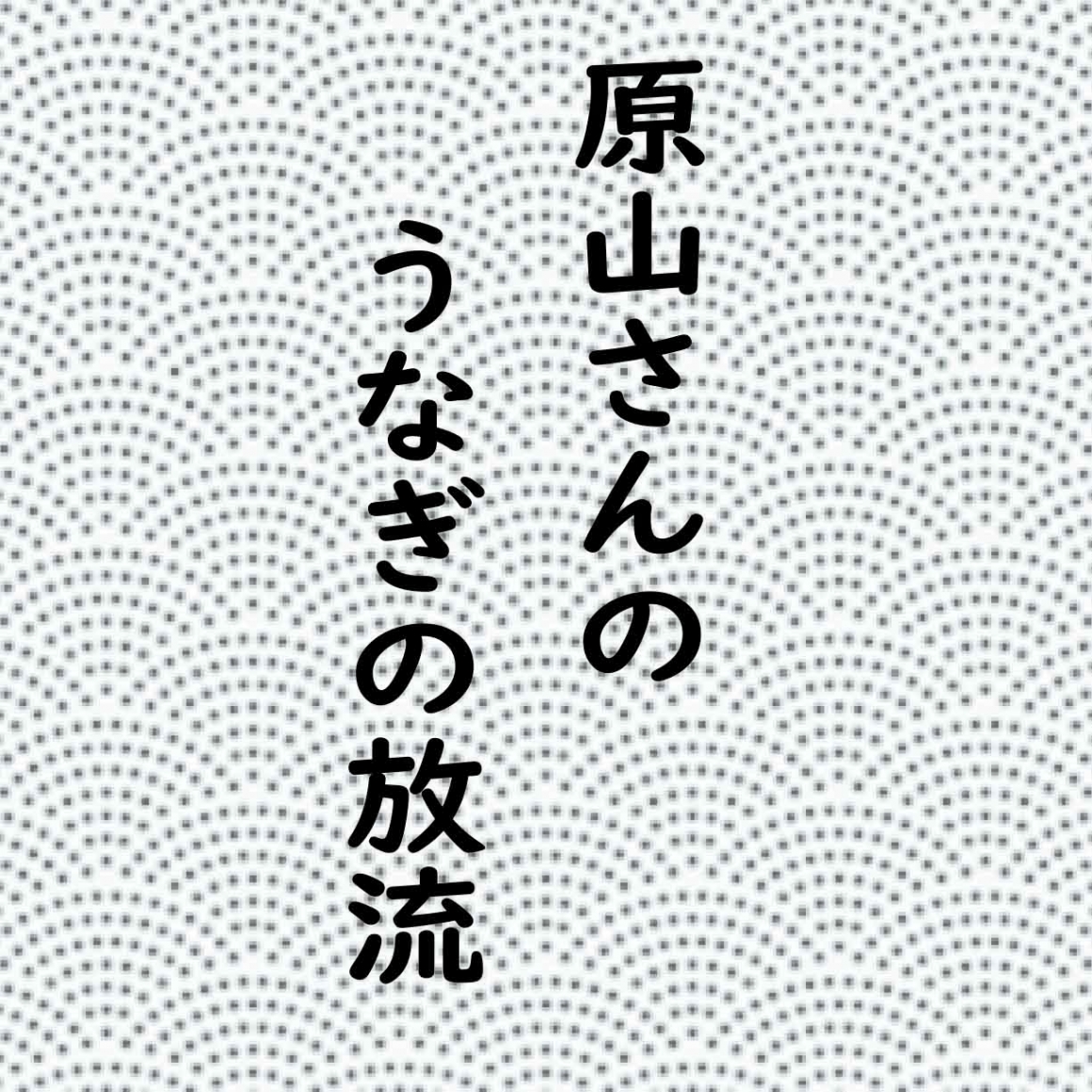
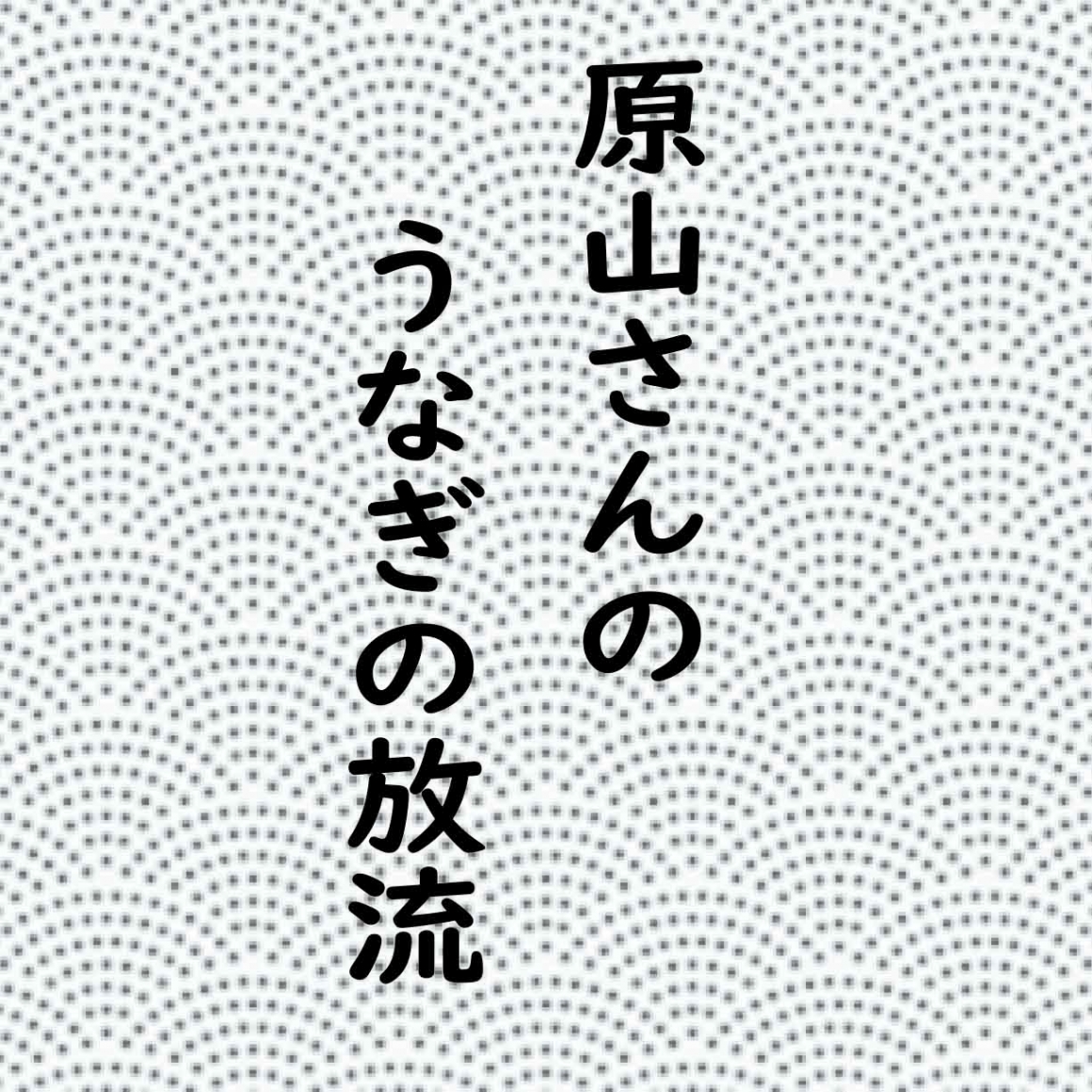
[概要] 甲府市美咲の 原山神社 では「うなぎ供養」と呼ばれる神事が行われる。これは、昔、原山神社 横を流れる相川が何回も氾濫したり、疫病が流行したり、地域の住民が難儀していました。そこに通りかかった行者が今の原山神社の所に祀られていた保食神の祠に生きたウナギを奉げ、祓い清めて相川に放流するように言った。その通りすると、疫病で腹を病んでいた人々が元気になったので、今でも「うなぎ供養」としてウナギの放流をしています。 原山神社 の名前は、「腹(原)を病ま(山)ない」から来ていて、安産とお腹の病気に御利益があると云われている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
原山さんのうなぎの放流
じじとばばさんが語ってくれました。
昔、昔、塩部の郷に悪病が流行り人々はたいへん難儀をしました。熱が出て体が腫れ、下痢もひどく、いくら薬を飲んでも、医者にかかっても治りません。たまたま通りかかった行者が、村人の悲しんでいるようすを見かねて、「これこれ村の衆よ、なにをそんなに悲しんでおじゃる」と聞きました。すると村人は藁をも掴む思いで、「実はもう十日あまり前から、あっちこっちに高い熱が出る病人が出て、いくら手当てをしても治りません。もう幾人がお寺さんに埋められたか知れません。どうぞお助けください」とすがりました。
行者はしばらく天の一角をじっとあおいでいましたが、「これは大変じゃあ、生霊のたたりだや、体の長い生霊だよ、甲府の城から乾(北西の方角)の方にあたるところに相川が流れている。そこのたもとの大欅の下に「保食神(うけもちのかみ)」を祀った祠がある。そこに生きたうなぎを捧げ、罪けがれを祓い清めて相川に放流をしてみそぎをなされ、三日後には悪病は退散する」というお告げをして西の方に去って行きました。
村人はお庄屋さんを先頭にうなぎを保食神に捧げ、相川に放流してみそぎ祓しをしました。するとどうでしょう、数日たたないうちに病人たちの熱は下がり腹痛もとまり、たちまち病は治って、昔の明るい郷になりました。
喜んだ村人は行者のお告げをありがたく長く伝えるため、ここに保食神を御神体として〝原山神社〟を建てました。このお偉い行者さまは、それから湯村山の地蔵尊に立ち寄り、途中金剛杖を大地に突き立てたそうです。すると不思議なことにここから温かい湯が湧き出しました。村人はたいへん喜んでそこに池を掘り、流れ出した温泉をここにためて、野良仕事の帰りに牛や馬とともに湯浴みして、一日の疲れを癒したそうです。
この話を終わると、じじとばばさんは間もなくこの世を去りましたが、原山神社のうなぎの放流祭りは今もなお続いています。
山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。