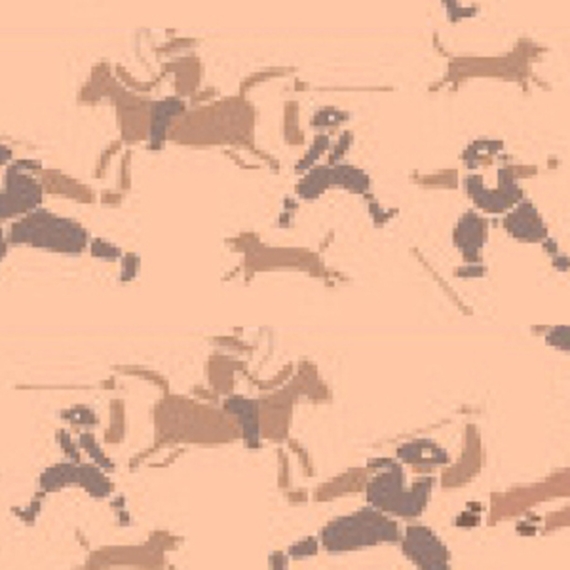物語
Old Tale
#1148
おいらん淵
ソース場所:甲州市塩山一之瀬高橋 おいらん淵(35.807544,138.856153)
●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2016年11月18日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。


[概 要] 昔、大菩薩峠の山中に黒川金山が有った。 一時は、鉱山関係者や、それにまつわる職業の者、それらの生活や娯楽に携わる者たちで、黒川千軒と呼ばれるほど、にぎわっていた。天正年間、武田氏の衰運と合わせるように、黒川金山の産出量も枯渇していき、金山の閉山が決まった。ただ、金は完全に枯渇していないかもしれない、新たな鉱脈が見つかるかもしれない。もし、敵に鉱山を奪われた後、鉱脈が見つかれば武田氏が再興することはかなわなくなる。閉山が決まってからは、坑道をふさいだり、鉱石の集積地を分からなくするなどの作業が続き、金山の場所は何もかも分からないようにされた。後は家を焼き払い山を下りるばかりになり、最後の宴が舞台を牛金淵の上に作り、華やかに行われた。宴もいよいよ最後となり、今まで鉱夫たちの娯楽を支えた花魁たちの総踊りが牛金淵上の舞台で始まった。それを合図に舞台を吊るす仕掛外され、花魁たちは全員が淵に落とされ、口封じされたと云う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
おいらん淵
県内には、金の採掘が行われたと伝えられるところが数多くある。これは戦国の世、武田が軍資金の多くを金の採掘によって賄っていたからで、黒川金山もその一つである。
黒川金山は、塩山市萩原の東北、大菩薩峠の山中にあるが、大菩薩峠は北都留郡丹波山村にまたがる山で、金の採鉱場や金掘り衆の小屋は丹波山村にまで広がっていた。
黒川金山が盛んな頃は、黒川千軒といって、大勢の金掘り衆慰安のための遊郭まである繁栄ぷりであったが、天正になって武田が衰運に向かう頃には金山の方も産出量がいちぢるしく減っていたために武田領としては遠い丹波山の黒川金山は閉山と決定された。
産金量は減っていたといっても、新たな鉱脈があるやも知れぬ金山の所在は敵方に知られたくなかった。閉山の日が決められると、坑口をふさいだり、選鉱場を始末したり、道具を焼いたり砕いたり埋めたりの作業で、大変であった。だが最後の宴は盛大にやることになっていて、みんな一生懸命に働いた。
始末はすべて終わり、あとは家を焼き払って山を下るばかり。長年の間働きなじんだ金山との別れの宴は、舞台を柳沢川の牛金淵の上に作り、川の両岸が見物席という趣向を凝らしたものであった。
金山奉行から労苦を謝し、「慰労の宴であり、別れの宴である。存分に飲め歌え」と挨拶があって、別離の宴は舞台での余興を楽しみながら、酒を酌み交わし、思い出に浸り、それぞれがさまざまな感慨を抱く中で進行していった。
金山の最後とあって、上下の区別なく、芸のある者は次々と舞台にのぼって芸を披露した。が、何といっても金掘り衆の余興の合間合間に行われる芸で磨かれたおいらんたちの踊りはさすがに見事で、やんやの喝さいを浴びた。
宴はおいらんの総踊りで締括られることになっていた。盆踊りを踊りながら舞台に上がり、勢ぞろいしたところで総見のあいさつをし、総踊りをすることになっていたが、総ぞろいし終ったときに、舞台を一挙に崩す仕掛けがはずされ、舞台もろとも五十五人の遊女は淵に落とされたのであった。
黒川金山の秘密が漏れることを恐れての処置であったが、このことがあって牛金淵は「おいらん淵」とも「五十五人淵」とも呼ばれるようになった。 今でも淵に臨めば、女の泣き声が聞こえるような気がするし、夕暮れ時など近くを通ると、異様な感じに襲われるという。
内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
悲劇的なお話であり、絵画的なお話であるので、有名になり心霊スポットのように言われたこともある。しかしこのお話は事実なのだろうか。口封じのためにわざわざ渓谷に舞台を作るというのでは確実に口を封じる手段としては合理的ではない。また金山の閉山の頃は遊女のことを花魁とは呼ばなかった。
だが、下流の丹波山には口封じされたと思われる遺体を供養したとの言い伝えがある。閉山に伴う口封じの殺戮なのか、過酷な鉱山労働中の事故なのか、秘密を伴う金山の運営に何か悲劇的な死があったのかもしれない。金山の秘密はいつしか美しい遊女たちの悲話として伝わっていったのではないでしょうか。
明治時代にこの地を訪れた役人が、秋の渓谷美を見て「花魁のように美しい」と言ったから「おいらん淵」と呼ばれたとも言う。現在、国道のバイパス化によりおいらん淵には立ち寄り難くなっています。しかし、周辺の渓谷は変わらず美しい姿を見せています。
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。