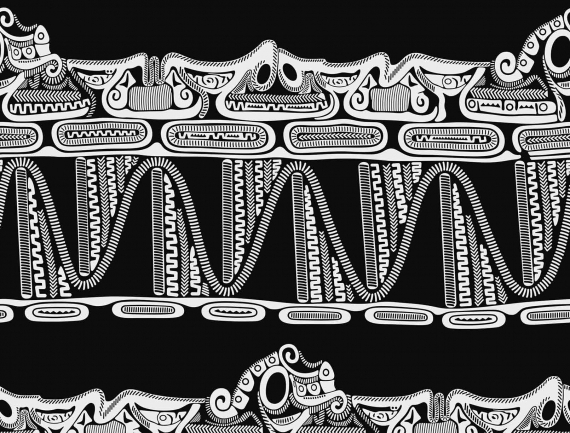物語
Old Tale
#1184
九一色衆十七騎
ソース場所:甲府市古関町
●ソース元 :・ 現地説明看板
・ 土橋里木(昭和51年)「甲州の伝説」甲州伝説散歩 ㈱角川書店 を参考にさせていただきました。
●画像撮影 : 2017年01月28日
●データ公開 : 2017年01月05日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。










[概 要] 古関は甲駿中道往還の間宿。 治承・寿永の乱以来、駿河と甲斐をつなぐ重要な軍事道路として機能していたため、武田氏は古関と本栖に関所を設置していた。戦国時代には特に重要な経路とされ、古関周辺には砦が築かれた。 武田の時代から甲斐の辺境警備のため武士団が置かれていた。これを九一色衆十七騎と呼ぶ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
口留番所跡は、昭和41年の台風26号による寺川の氾濫で、周囲の土地ごと大きく削り取られてしまったので(本郷橋手前にあったそうだ。今、台風被害の慰霊碑が立っている所から橋の袂の石尊神社の辺りか)昔の姿を想像するのは難しい。寺川沿いに精進湖のほうに古道が延びていたそうである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上九一色村指定史跡
土橋大蔵の石廟(上九一色村古関 昭和六十年三月三十日指定)
土橋大蔵は、武田時代に九一色郷に居住した地頭で九一色衆十七騎の一人といわれ、その屋敷跡は、この石廟周囲の田圃であると伝えられています。
左下の低地がその墓跡で、水田とするために石廟も現在地に移されました。
また、この石廟は桃山時代の特徴をもつもので、石造美術としても注目されています。
現地説明看板より(この石廟は田畑のあぜ道を入った所にある。近づく際には地域の人にことわって、足元に注意してください。)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
九一色郷古関の地頭として豪勇の聞こえが高かった土橋大蔵尉には、彼の忠犬と地域のお正月にまつわるこんな話も伝わっている。
ある年の正月に彼は愛犬二匹を連れ鹿狩りに行った。その際足を滑らせ彼は谷底に転落してしまった。一匹は主人の番をし、もう一匹は屋敷に飛んで帰って主人の事故を知らせた。
彼の葬儀は正月四日に行われ、その日は松飾一切を取り払ったのでそれ以降古関では正月四日には松飾を取り去り、お正月様を送るようになった。
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。