


物語
Old Tale
#0538
善光寺 棟木の由来
ソース場所:甲府市善光寺3-36 善光寺
●ソース元 :・ 山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」
・ 現地説明板
●画像撮影 : 2017年02月04日
●データ公開 : 2016年06月24日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。


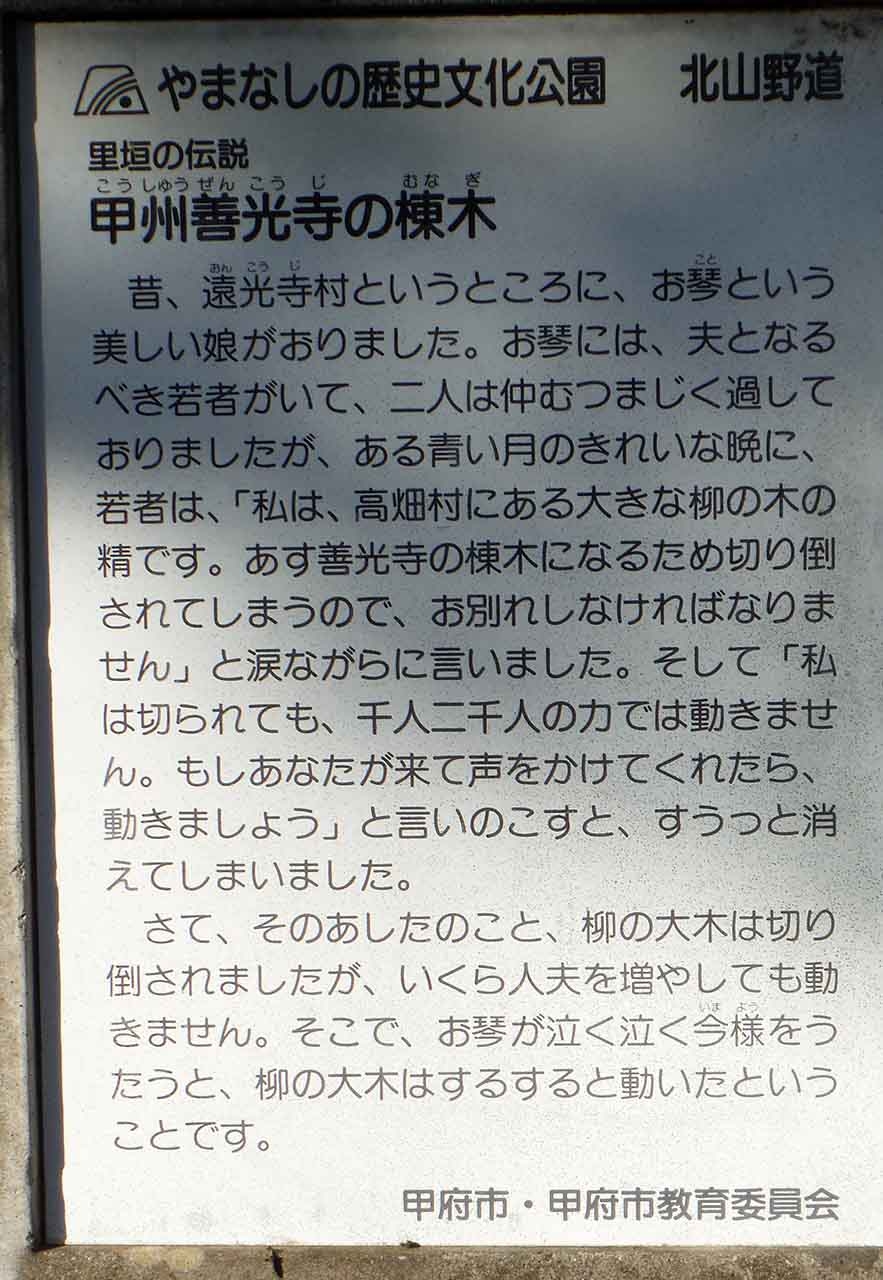
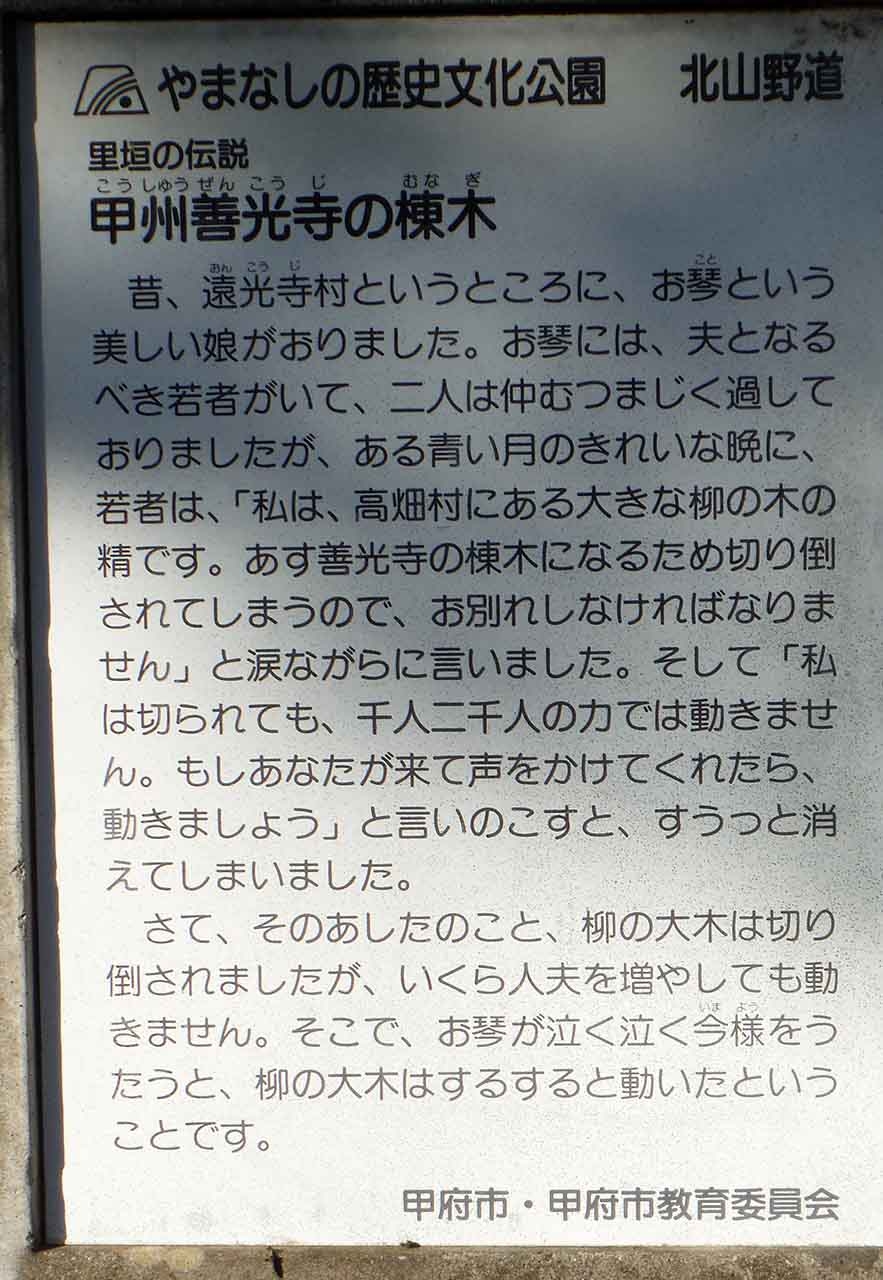






[概要] 信玄が甲斐善光寺の本堂を建てた時、その壮大な建物に使える棟木にふさわしい巨木がなかなか見つかりません。やっと見つけた大柳の木を切り倒し、大勢の人夫を使い運ぼうとするもびくともしません。 大柳と美しい娘の不思議な恋のお話がありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
善光寺、棟木の由来
その昔、甲府郊外板垣の里(善光寺町)に甲斐の国の武将、武田晴信(信玄)を開基とした、定額山善光寺が建てられたのは永禄八年のことでした。人母屋造りの本堂は横十五間余、奥行二十五間余もありましたので、棟木にする大木はなかなか見つかりませんでした。ところが甲府の南、荒川辺りの高畑村(今の国母)に梁(やなぎ)の大木があることが判りました。普請奉行はたいへん喜びました。その頃、隣の遠光寺村(今の伊勢町)の百姓に一人娘があって、気立ては優しく姿も美しい可愛い娘さんでした。近所の評判もよく親孝行者でした。
いつの頃からか彼女のもとに一人の若者が通ってくるようになりました。娘は、はじめは恥しいやら恐いやらで、口もろくろくきけませんでしたが、いつしか若者の親切にほだされて、毎夜たずねて来てくれるのが待ちどおしくなるようになりました。もう別れることの出来ない仲になりました。どうしたことか、今宵たずねてきた若者は いつもとちがい、沈みがちの顔には涙さえ浮べています。びっくりした娘は、一体どうしたのかとたずねると、若者はせっかく親しい仲になったのに、今宵かぎりでお別れだと申しました。娘はおどろき悲しんで「あなたの行くところなら、どこへなりとついて参ります。わけを話して下さい。」とよよとばかり泣き崩れました。「実は私はただの人間ではなく、高畑の梁の精です。お前の真心と優しさに夫婦約束までしたが、こんど善先寺の棟木になるため、明日は伐られて千年の命を絶たれることになったのです。伐られて運ばれようとも、村の人の力では動きません。そのときお前が現れて一声こえをかけてくれれば、難なく動き出します。末ながく幸せに暮してくれ。」というや、若者の姿は消えてしまいました。
いよいよその日になりました。 たくさんの人夫が来て梁の木を伐り倒して枝を払い丸太にし、綱をつけて運ぽうとしましたが、丸太はビクともしません。普請奉行の役人も人夫も困りはてていると、そこへ娘が現れて、一声こえをかけると、不思議や大木はスルスルと動き出し、無事に板垣の里まで運ばれて善先寺の本堂は見事に完成し、開基の晴信公をたいへん喜ばせ、娘に褒美を賜ったことはいうまでもありません。
山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
やまなしの歴史文化公園 北山街道 里垣の伝説
甲州善光寺の棟木
昔、遠光寺[おんこうじ]村というところに、お琴という美しい娘がおりました。お琴には、夫となるべき若者がいて、二人は仲むつまじく過ごしておりましたが、ある青い月のきれいな晩に、若者は、「私は、高畑村にある大きな柳の木の精です。あす善光寺の棟木になるため切り倒されてしまうので、お別れしなければなりません」と涙ながらに言いました。そして「私は切られても、千人二千人の力では動きません。もしあなたが来て声をかけてくれたら、動きましょう」と言い残すと、すうっと消えてしまいました。
さて、そのあしたのこと、柳の大木は切り倒されましたが、いくら人夫を増やしても動きません。そこで、お琴が泣く泣く今様[いまよう]をうたうと、柳の大木はするすると動いたということです。
甲府市・甲府市教育委員会 (境内の説明板より)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このような不思議なお話が伝わっていますが、残念ながら信玄の建てた本堂は宝暦四年(1754年)火災によって焼失してしまいました。その後30年余りの年月をかけ、寛政八年(1796年)再建されました。これが今に残る物で、桁行 約38m、梁間 約23m、高さ 約26mと東日本最大級の木造建築物です。壮大な建築物ですが、信玄の造った最初の本堂はさらに大きかったそうです。 見た事もなければ、想像も及ばないような大木が使われました。
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。


















