


物語
Old Tale
#0528
孫見祭
ソース場所:富士河口湖町河口1 河口浅間神社
●ソース元 :・ 河口浅間神社 由来書、例大祭案内を参考にしました。
●画像撮影 : 2015年11月04日
●データ公開 : 2016年04月01日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。








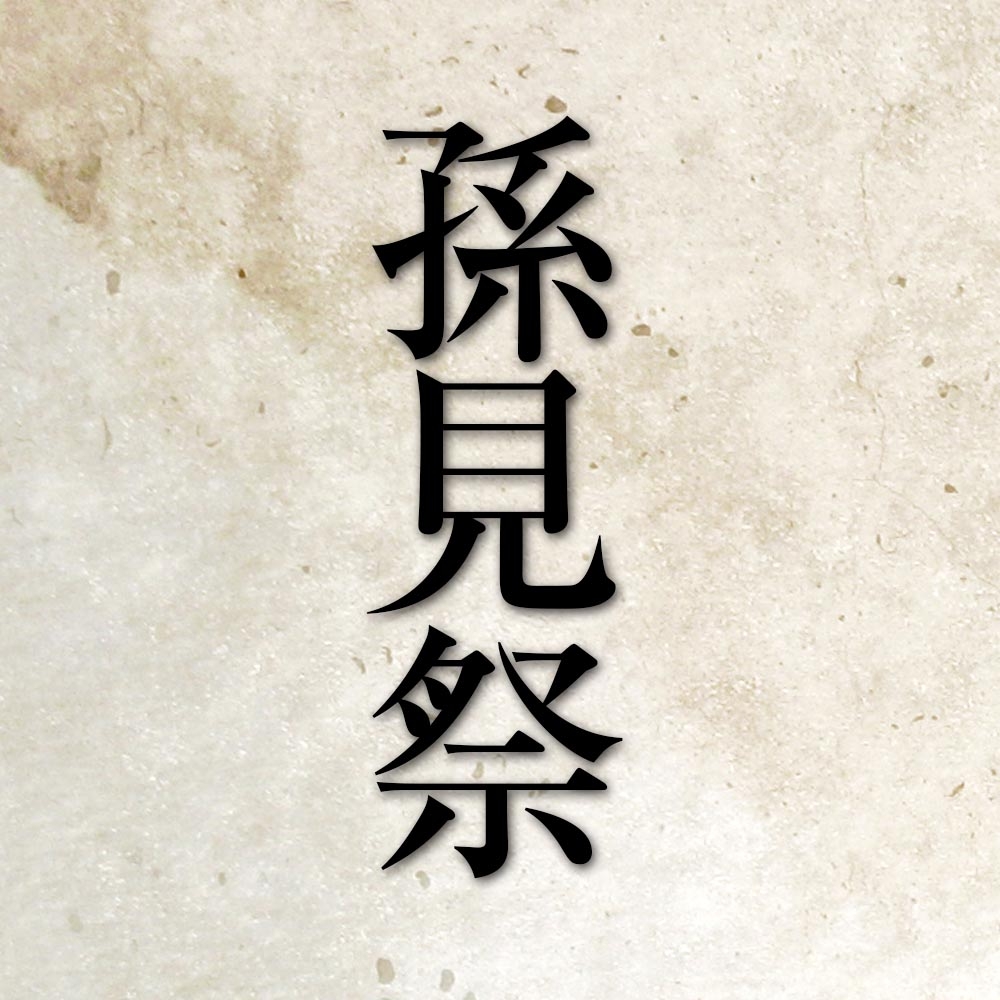
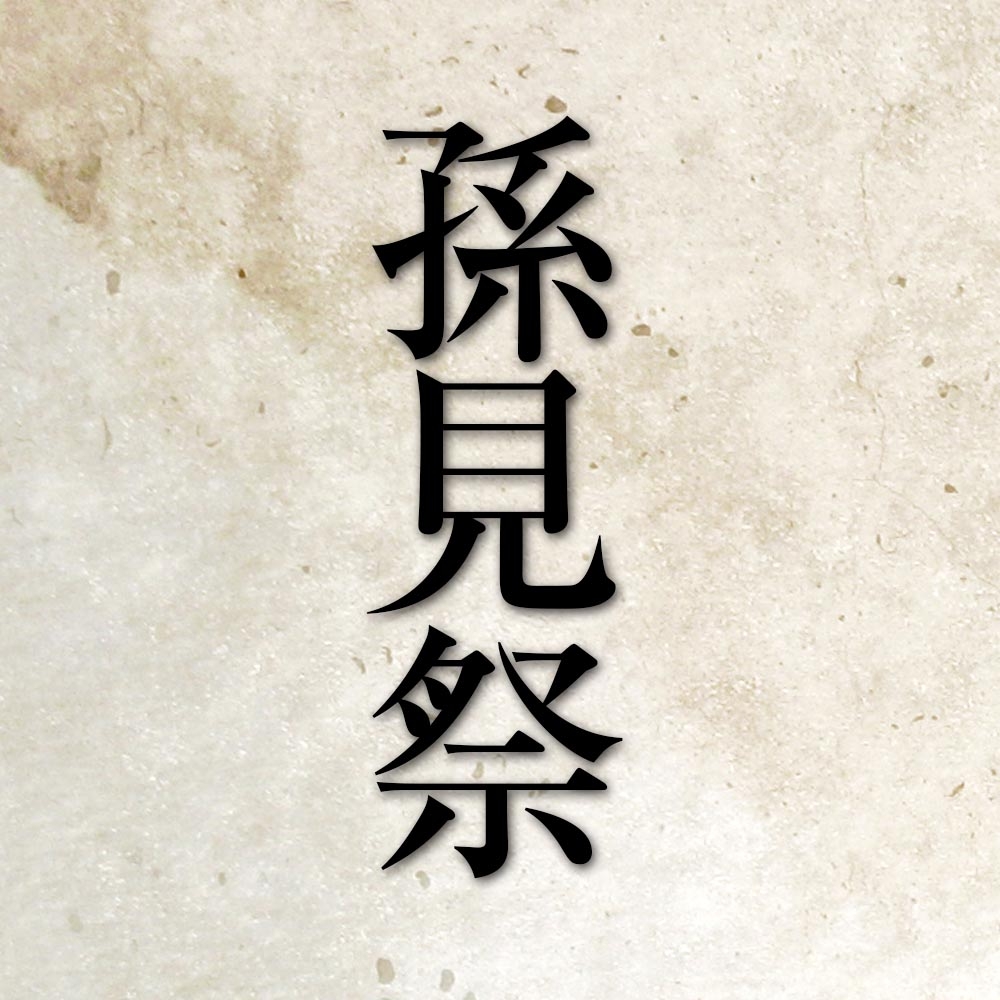
[概 要] 河口浅間神社の例大祭は、富士山の神である木花開耶姫命が孫の誕生をお見舞いしに御神幸されるという祭り。県指定無形文化財「稚児の舞」が奉納される。またこの祭りの時に欠かせない郷土料理として「めまき」というものがある。魚を芯にして富士山を模して三角にアラメ(コンブ科アラメ属の大型海藻)を巻き、醬油や砂糖でじっくり煮込んだものである。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
孫見祭 河口浅間神社の例大祭。この神社の祭神は浅間大神(木花開耶姫命を指す)である。孫見祭とは木花開耶姫命の子どもである彦火火出見尊(ヒコホホデミノミコト)と、彼の皇后 豊玉姫命の間に御子が生まれたので、これを姑神の浅間様(木花開耶姫命)がお見舞いに御神幸されるという祭。境内から御神輿と共に河口湖湖畔の産屋ヶ崎神社に向かう。
貞観六年(864年)富士山大噴火により、富士北麓にあった大きな湖「せのうみ」が埋没してしまうような甚大な被害があり、多くの人命が失われた。翌貞観七年、河口浅間神社は富士山噴火の鎮祭のため建立された。
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。


















