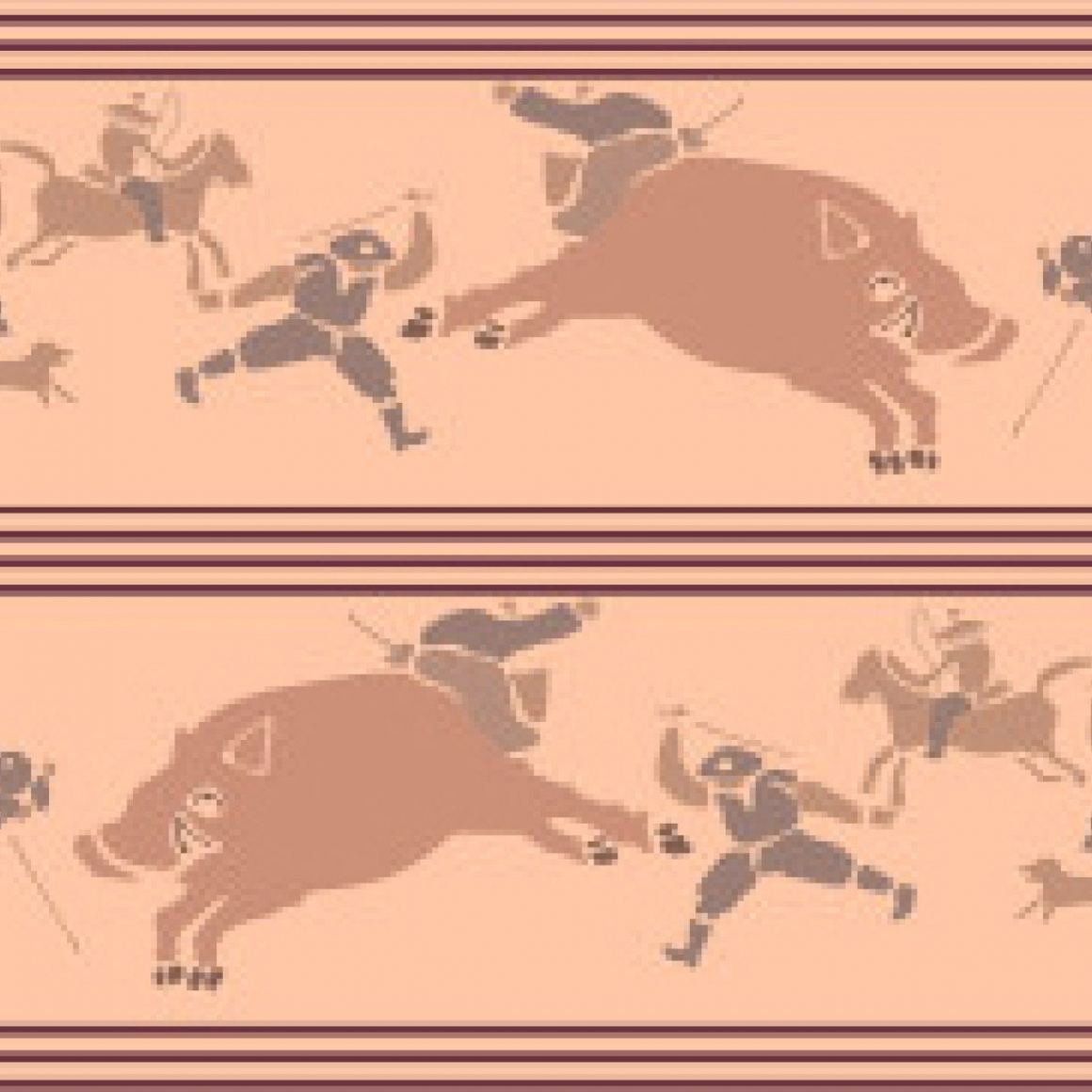
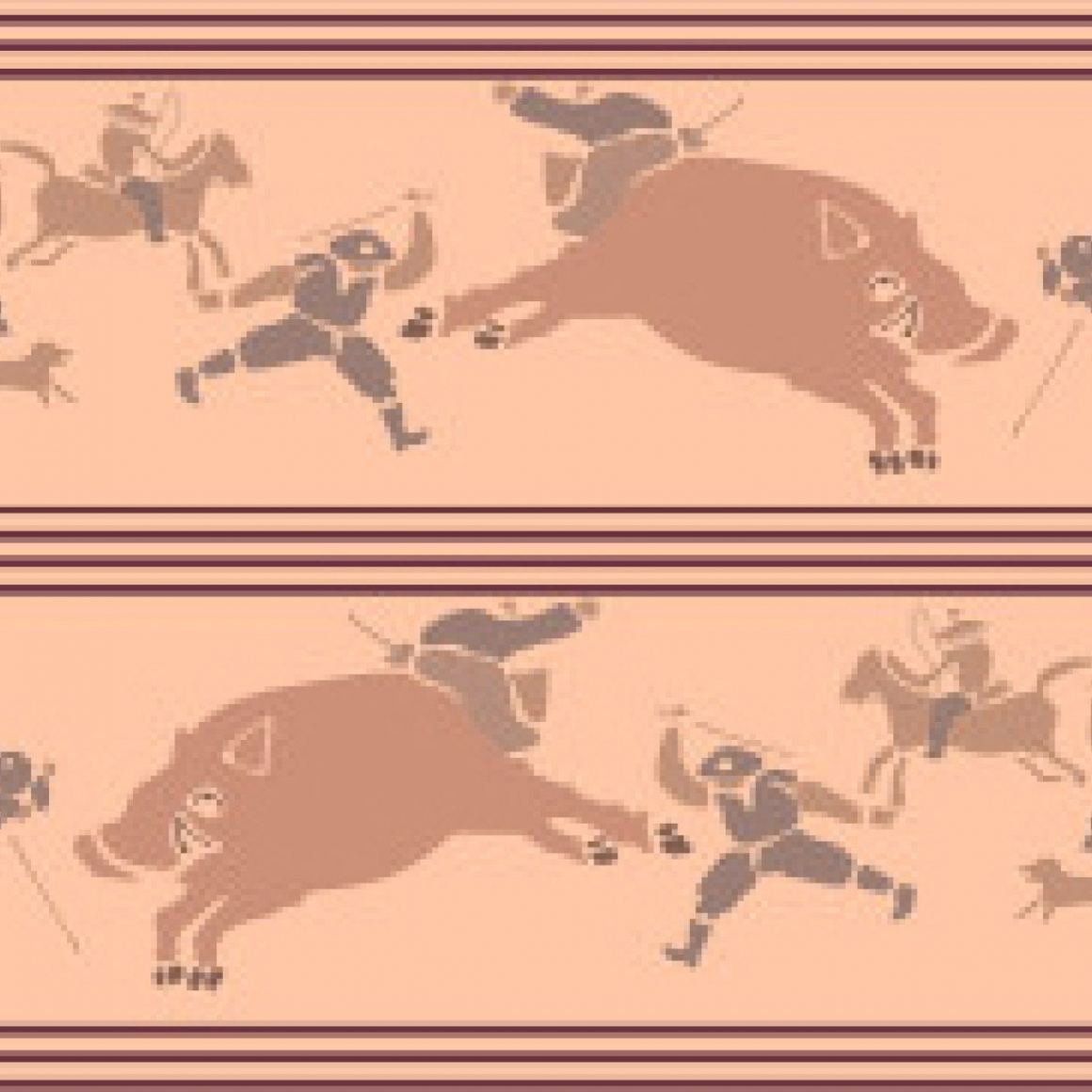
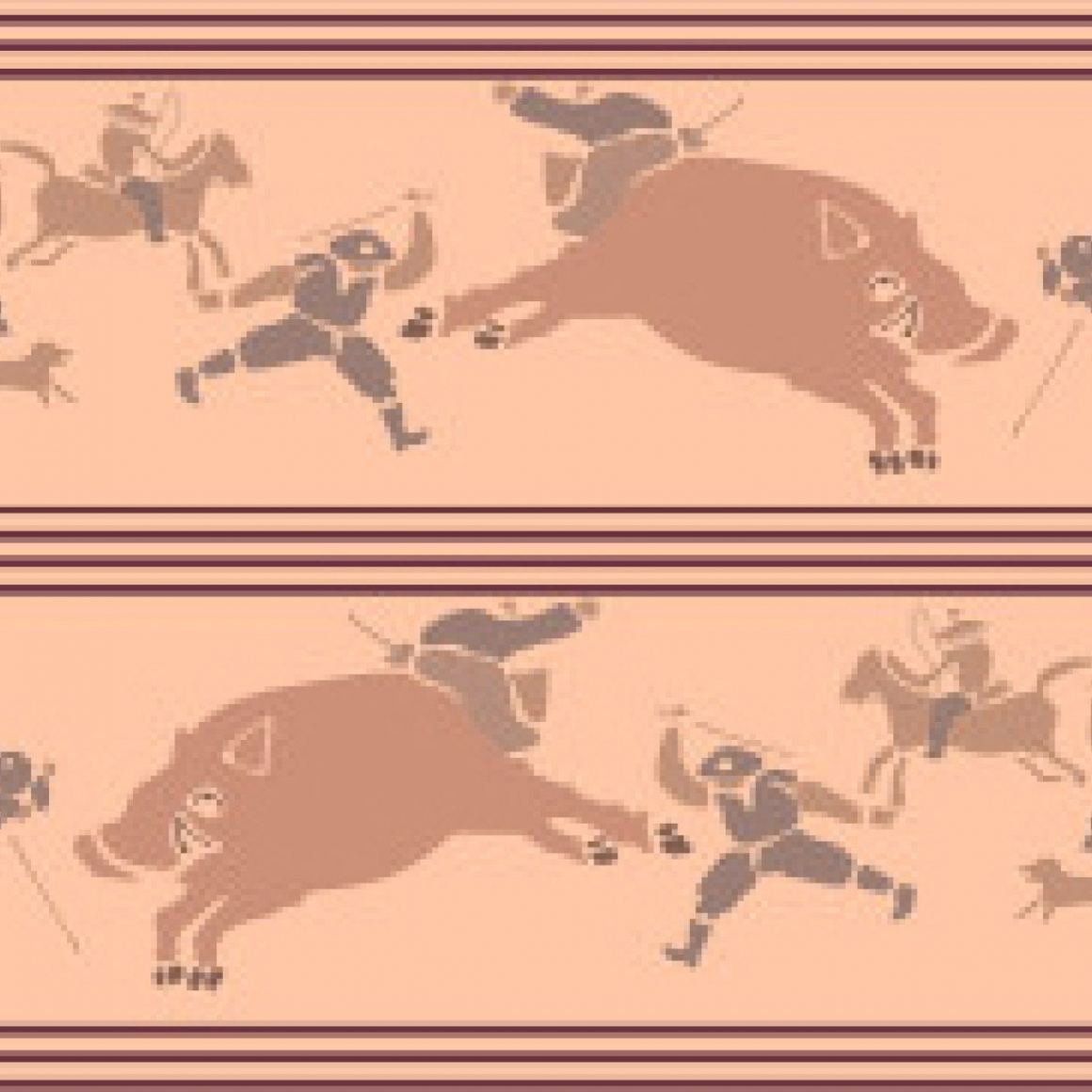
物語
Old Tale
#0557
矢立の杉
ソース場所:大月市笹子町黒野田
●ソース元 : ・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開: 2016年06月24日
●提供データ: テキストデータ、jpeg
●データ利用: なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
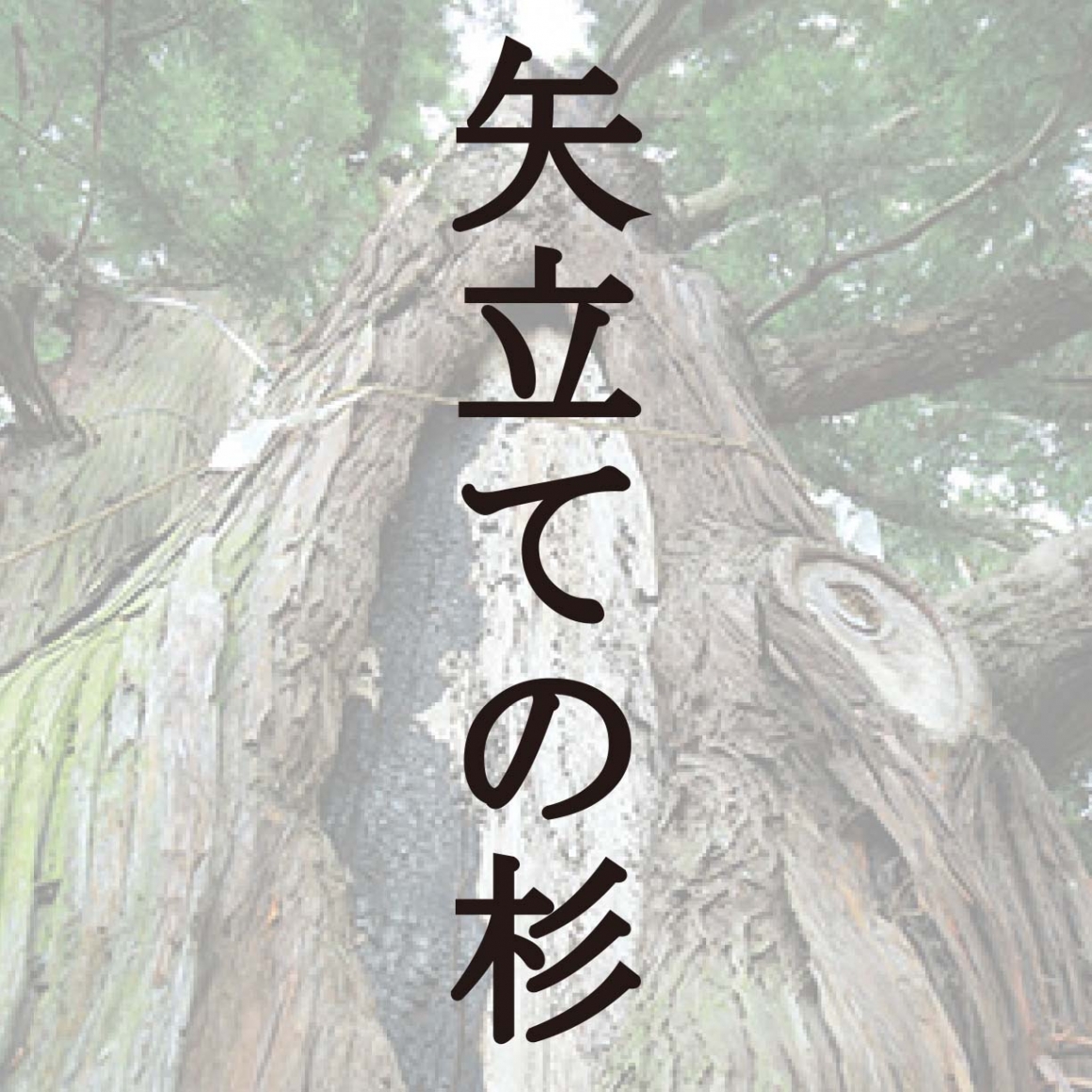
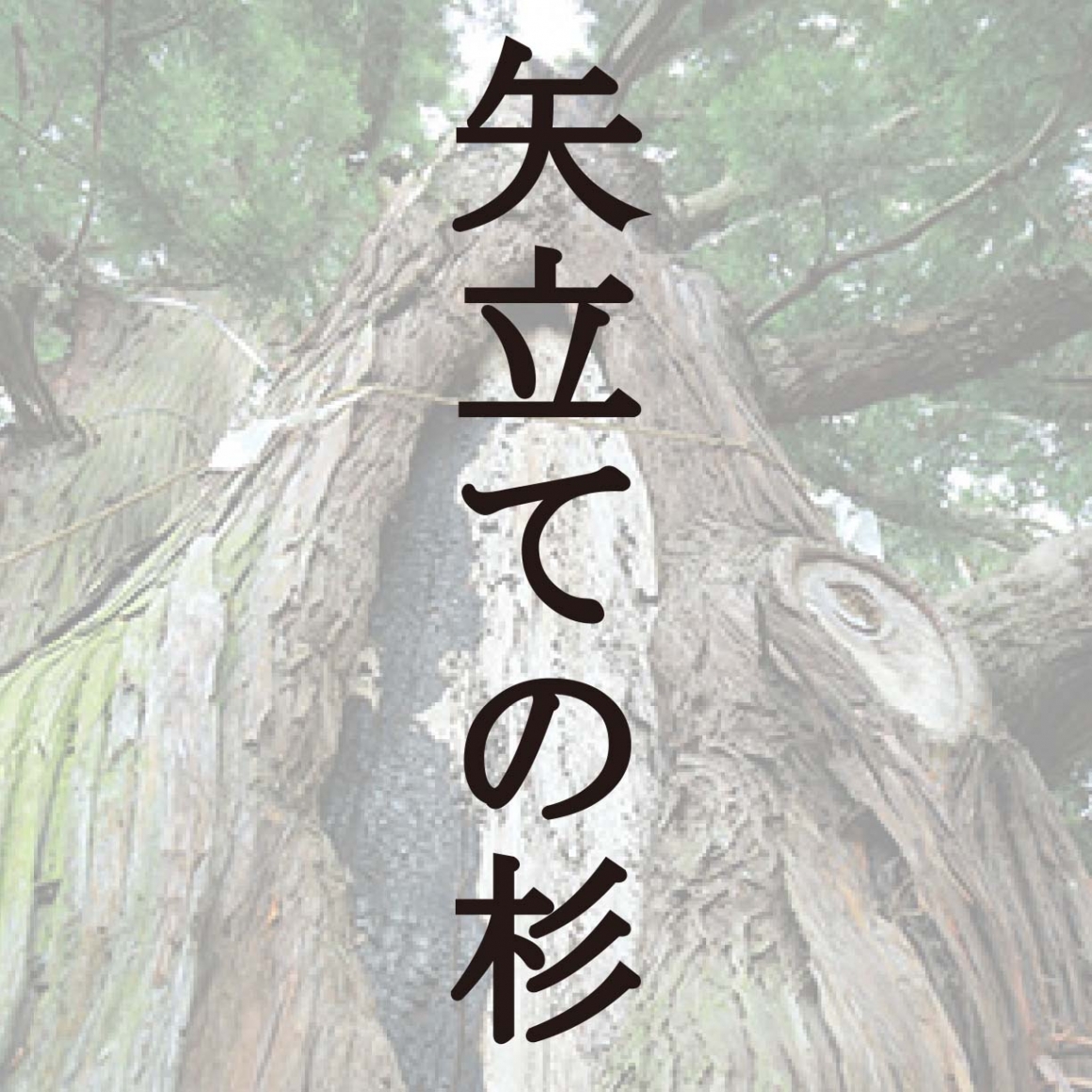
[概 要] 国道20号の笹子トンネルを避け、甲府側からは鶴瀬宿の辺りから、大月側からは笹子トンネル手前を山梨県道212号日影笹子線に入る。この道は1958年に笹子トンネルが開通するまで甲府盆地と首都圏を繋ぐ主要道路でした。古くから甲州街道一の難所と言われた笹子峠を越える街道に沿って繋がれた道路でした。この県道の中程、やや大月寄りに杉の巨木があります。樹齢1000年とも言われ、源為朝や源頼朝ゆかりの杉とも伝わり、戦国時代には合戦に赴く武士が故事にあやかり戦勝祈願のためこの杉に矢を射立てたと伝わります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
矢立の杉
「岩殿山で国見れば国恋し矢立の杉が見え候」
と俚謡に伝わる矢立の杉とは、笹子峠から一キロほど東へ下った沢沿いに立つ大杉である。
幹囲二丈七尺七寸、人が手をつないで七抱え半あるといわれるこの杉は千年をはるかに越える歳月を通して、さまざまな歴史を眺めかつ体験してきた。
保元の乱でやぶれた為朝は流地伊豆から逃れて 滝子山にかくれ住んだが、強弓を引くことで人に知られた力を衰えさせまいと時折弓を引いた。ある日、滝子山の頂上にたち見渡すと、その頃はまだ坂東山と呼ばれていた笹子峠に一きわ大きくそばだつ杉が眼についた。為朝は百人力といわれる強弓をきりきりと引きしぼり、この大杉めがけて矢を放った。矢はねらいたがわずこの杉につきささったという。
それからしばらくたって頼朝が将軍となって富士の巻狩りをした折、笹子峠のあたりまで獲物を求めて来た武士たちが大木を見ておどろき「よき標的」と、遠的の試し矢を放っと見事命中、それからというもの、ねらった獲物は必ず射あてるという霊験があった。
こんなことがあって誰いうとなく矢立の杉と呼ぶようになり武士の間に縁起の杉として噂がひろがった。武士達はここを通る度に頭を下げ「南無八幡大菩薩」をとなえて矢を放ち、武運と戦勝を祈願するのであった。
武田信満の軍勢が禅秀の乱でここを通過するとき、武運の吉凶占いに矢を放ったところ、突然の風に矢が流されて杉に当らなかった。家臣筆頭の手だれであったので、放った直後の風のせいとはされたものの、不吉な思いは木賊山(天白山)での敗戦となって証明され、矢立の杉の霊威が示された。
この杉は参陣の吉凶を見るだけでなく道しるべともなった。岩殿城は小山田の城ではあったが武田に臣従したので、武田からも目付の城番が派遣された。城番ははるかに見える矢立の杉を見ては、通って来た道を思い、あの杉の向こうに古里のあることをしのび、「国恋し」と望郷の念にかられるのであった。
武夫(もののふ)のたむけの征箭もあとふりて
神さび立てる杉の一もと
杉の傍にある石碑は平和の訪れた明暦年間のものである。
内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。


















