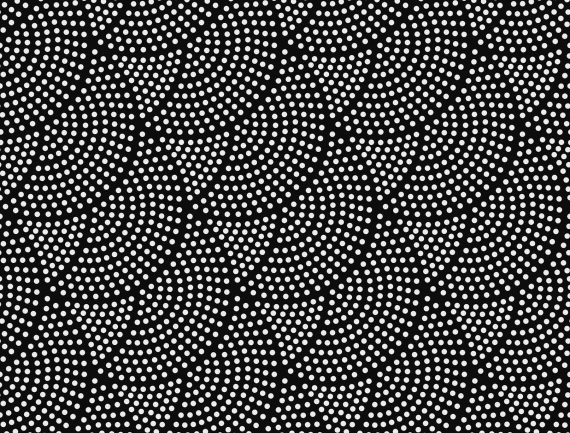物語
Old Tale
#1565
天長山 光明寺 (山梨市上神内川945)
ソース場所:光明寺 山梨市上神内川945
●ソース元 :・ 甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 (参照 2024-08-27)
・ 現代語訳 吾妻鏡 五味文彦・本郷和人 編 参照
●画像撮影 : 年月日
●データ公開 : 2020年08月26日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
[概要] 山梨市上神内川の光明寺の薬師仏は、寺内の当帰の木(当帰はセリ科の薬草。木の種類ははっきりわからないが、薬草と同様な名前を記載しているので、寺内にあった薬効のある樹木と思われる)の根元から出て来たと伝わる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
光明寺 東郡神内川村 浄土宗
薬師仏あり。
昔、この寺内に大広という所があった。寛永年中、この大広に一本の当帰の木が生えた。 その頃、三澤玄昌という武田侍の末裔が、侍から一井の人となり医者をしていた。すると夢に「大広の当帰の木の下を掘ってみろ」と言われた。すぐに光明寺の住職と一緒にその地へ行き、当帰の根を掘ってみると、木像の薬師が出てきたのでそこに堂を建てて、大広寺と号した。
この像を古仏に詳しい人に見せると、聖徳太子の作に間違いないという。また、この寺に、中御門黄門の姫君の廟所あり。石碑に、竹に雀の紋が付いているが、どんな由来なのか、昔の事でよくわかっていない。
(「裏見寒話」 巻之二 府中寺院 の項より)
【裏見寒話とは、野田成方が甲府勤番士として在任していた享保九年~宝暦三年(1724-1753)までの30年間に見聞きしたり、調べた甲斐の国の地理、風俗、言い伝えなどをまとめたものです。只々聞いたものを記すだけでなく、良く考察されており、当時の様子や、一般の人達にとって常識だった歴史上の事柄を知ることが出来る。】
当帰の木 薬草の当帰はセリ科の多年草なので、同様な薬効のある木であったか、「当帰芍薬散」という方剤はよく使われていた様なので、芍薬の木の間違いなのかわからない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
光明寺は古くは 天長山 東漸寺 と言ったそうです。武田三代(信虎・信玄・勝頼時代)の頃、この地域は城氏の領地で、城氏の菩提寺とも伝えられています。城氏は平安時代から鎌倉時代初期に越後国に栄えた平氏の末裔と思われる。戦国時代の武将であった城景茂(1546-1610年)は、上杉謙信に仕えていたが、謙信の不興を買い、永禄三年(1560年)より武田氏に仕え、以後 足軽大将として多くの戦功をあげたと伝えられています。武田氏が滅びた後は、徳川家に仕えたという。 (阿部猛・西村圭子 編「戦国人名事典」 新人物往来社)
平安時代後期、城氏は、保元の乱においては平清盛に従い活躍するも、平氏の没落とともに徐々に衰退し、越後の城氏の所領は、後には安田義資(安田義定の子。アーカイブno.1543参照)の所領となった。しかし、文治五年(1189年)の奥州合戦においては、当時預かり囚人であった城長茂のことを、鎌倉幕府の中枢にいた梶原景時が源頼朝に推挙し、その活躍から城氏は幕府の御家人になる。越後国北部を治めるようになったようだ。しかし、頼朝の死後、幕府内で影響力を強める北条氏と、二代将軍 源頼家を推す勢力のパワーバランスが崩れ、正治二年(1200年)城氏を庇護してくれていた梶原景時が失脚し滅ぼされてしまった。正治三年(1201年)城長茂は、梶原景時を陥れた鎌倉幕府の御家人たちに弓を弾こうと立ち上がった。景時追放の首謀者の一人 小山朝政が京都守護役で在京していたので、その邸宅を襲撃し、その後、土御門天皇の御所に向かい、鎌倉幕府追討宣旨を要請するも断られると、京都に潜伏した。この騒ぎを治めるため建仁元年(1201年)二月十三日朝廷は改元を行った。それでこの城氏の蜂起を「建仁の乱」と呼ぶ。また、長茂の蜂起に呼応して越後国でも甥の城資家らが立ち上がった。資家には長茂の兄妹であり、資家の叔母であり弓の使い手として有名な 板額御前(アーカイブno.343参照)が付き添い、驚くほどの活躍を見せました。それ以降、城氏は歴史の表舞台からは見えなくなってしまったのですが、平安時代から鎌倉時代にかけての陰謀渦巻く様子を見ていると、判官びいきではありませんが、力を持ちながらも陰謀に潰されていった甲斐源氏の武将たちや、城氏・板額御前のような武人達に肩入れしたいような気になっていきます。城景茂が建仁の乱で活躍した城氏の系譜かどうかは知らないが、400年後の甲斐の国にその名を見つけて、わくわくした。
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。