


物語
Old Tale
#1584
燈籠仏(甲府市善光寺3-36-1 善光寺本堂内)
ソース場所:甲府市善光寺3-36-1 善光寺本堂内
●ソース元 :・ 甲斐善光寺hp
・ 「甲斐志料集成3」甲斐志料刊行会 編 ・甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 (参照 2024-08-28)
●画像撮影 : 2017年02月04日
●データ公開 : 2021年07月12日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
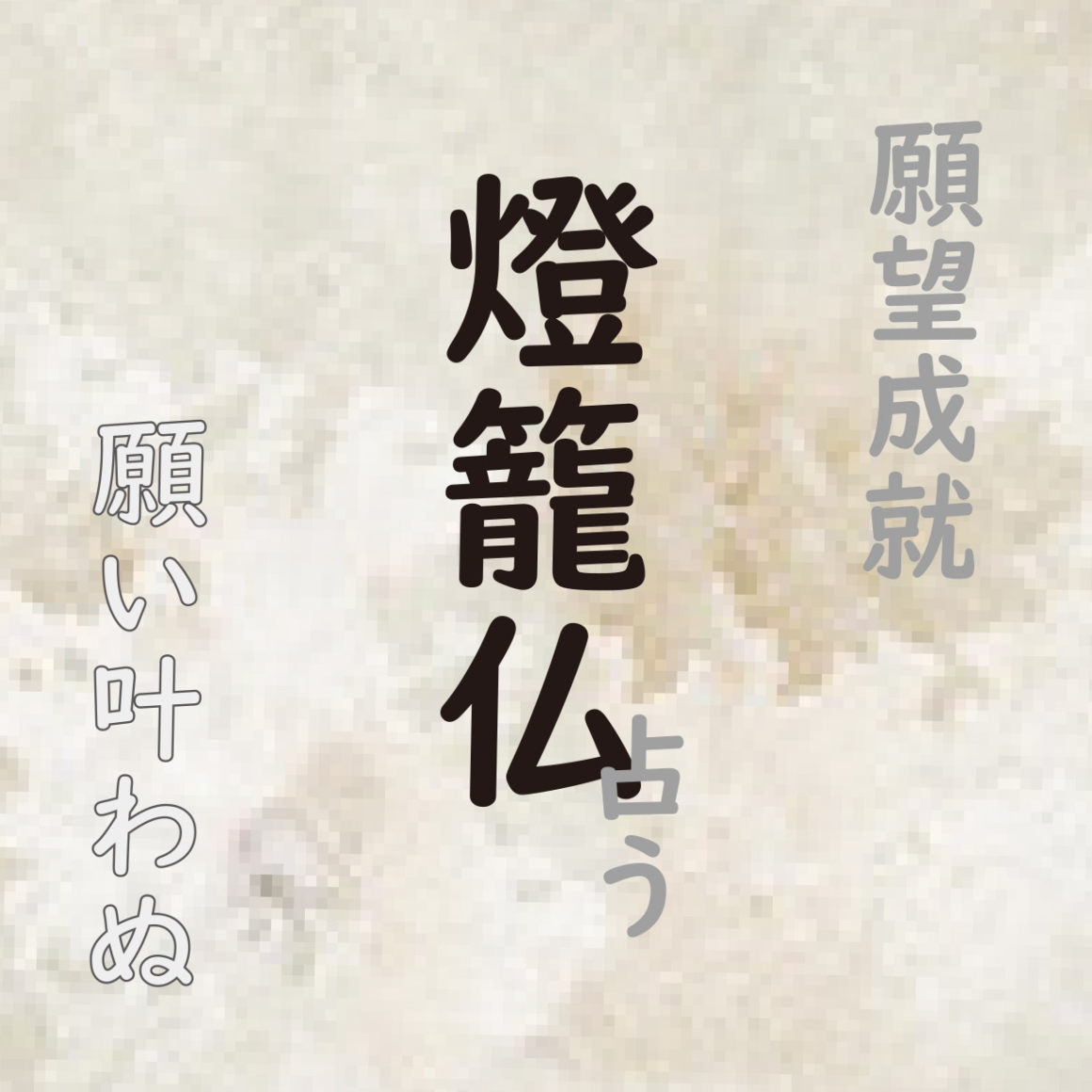
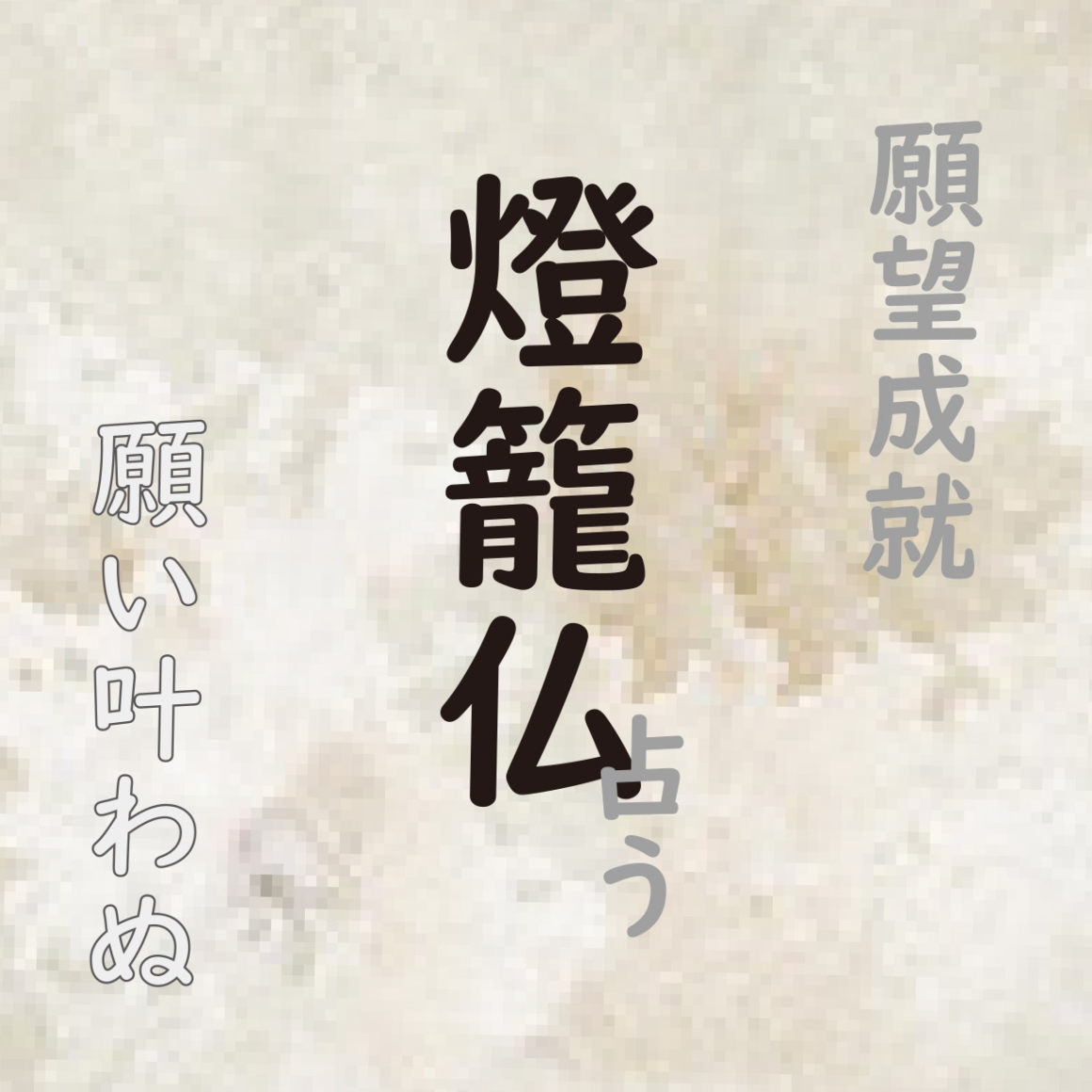




【概要】 甲斐善光寺には燈籠仏と呼ばれる秘仏が祀られている。善光寺には金堂や山門、ご本尊、鳴き龍、など見るべき物はたくさんありますが、聞きなれない仏像です。しかし、江戸時代この燈籠仏は大変な霊力があるとされ、甲斐国内だけでなく、京や江戸にも幾度となく出開帳が行われるような有名な仏像だったそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
涅槃堂・燈籠仏
黄金仏なり、丈 一寸八分(およそ5.4cm)。銅燈籠の中に置く立像。この彌陀は知恩院御門跡の封印がある。僧侶もみだりに拝することは出来ない。衆人一人で決め難い事がある時、一心に拝し、この燈籠を手で持ち上げ、その軽い・重いで事を占う。実に霊仏である。 ( 「甲斐志料集成3」甲斐志料刊行会 編 p147 「裏見寒話」巻之二 仏閣 の項より)
この燈籠仏は霊力があるとされ、甲斐国内のみならず、江戸や京都でも出開帳が行われていた。歌舞伎のセリフや川柳にも登場するようになり、知名度も高かった。
明治六年(1873)、山梨県令・藤村紫朗により「山梨郡善光寺燈籠仏を以って、吉凶禍福をトするを禁ず」との通達が出され、燈籠仏占いが衰退していった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
甲斐善光寺
甲斐善光寺は甲府市善光寺にある浄土宗寺院。
いわゆる戦国時代の天文年間、武田晴信(信玄)は信濃侵攻を本格化させ、北信濃を庇護する越後の長尾景虎(上杉謙信)と衝突し、北信濃において複数回の戦闘「川中島の戦い」を繰り広げた。天文二十四年(1555)七月の戦いでは戦火が信濃善光寺に及んだ。弘治元年閏十月十五日、駿河の今川義元の仲介により一旦和睦が成立し、武田、上杉双方は川中島を撤退する。この時、景虎は信濃善光寺 大御堂本尊の善光寺如来や寺宝を越後に持ち帰り直江津に如来同を建設した。これに対し、晴信は弘治三年善光寺北西の葛城城を落とし、一帯を勢力下におくと、善光寺別当の栗田寛久に命じ、信濃善光寺本尊の阿弥陀如来像や寺宝を甲斐國に運ばせた。善光寺如来は永禄元年(1558)九月甲斐に到着し、甲斐善光寺が創建された。
甲斐善光寺の造営工事は10年以上の長期間に渡る大規模ものだったという。この信玄の創建した善光寺は、「宝暦四年二月七日、門前の農家より出火。山門・本堂・方丈・鐘楼・三重塔・など東頬の房の中で焼け残った建物は何もなかった。或る話によると勝頼没落の時、川尻(川尻秀隆)の軍兵がやってきて、勝頼父子が潜んでいるのではと疑い本堂に火をかけたが、焼け落ちる事はなく、御仏の奇跡と言い伝わっていた。なのに、今回の消失を国中挙げて嘆き惜しんでいる。」「(その本堂は)飛騨の匠の技をもって造られた大伽藍で、先年消失した信州善光寺を再建する時に甲斐善光寺のように造ろうとし、番匠(工事担当技術者)を遣わして堂の造りを見せたが、梁を使わず造るなんて当時の技術力が余りに高く、同じには造れないと空しく帰国した」というような伽藍だったことが「裏見寒話」に記されている。現在の金堂・山門は寛政八年(1796)に再建されたもので、金堂も信玄時の規模には至りませんが、撞木造り 総高27m、総奥行49mという、日本有数の木造建築として、山門と共に国の重要文化財に指定されています。
また、信玄が運ばせた善光寺如来像だが、武田氏が滅亡後、岐阜城城下、清州城城下、三河国など当時の権力者の移り変わりに従い、各地を転々とした。慶長伏見地震により京都東山 方広寺の大仏が倒壊し、豊臣秀吉は再度京都に大仏を建立しようとした。この時も、大仏の代わりとして甲州から借り寄せられ大仏殿に安置されたが、大仏の不思議なお告げがあり、翌年信州に返され、今は信濃善光寺に鎮座している。甲斐善光寺では、前立仏を新たに御本尊と定め現在に至っています。 (甲斐善光寺hpより / 「甲斐志料集成3」甲斐志料刊行会 編 p147 「裏見寒話」巻之二 仏閣 の項より)
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。

















