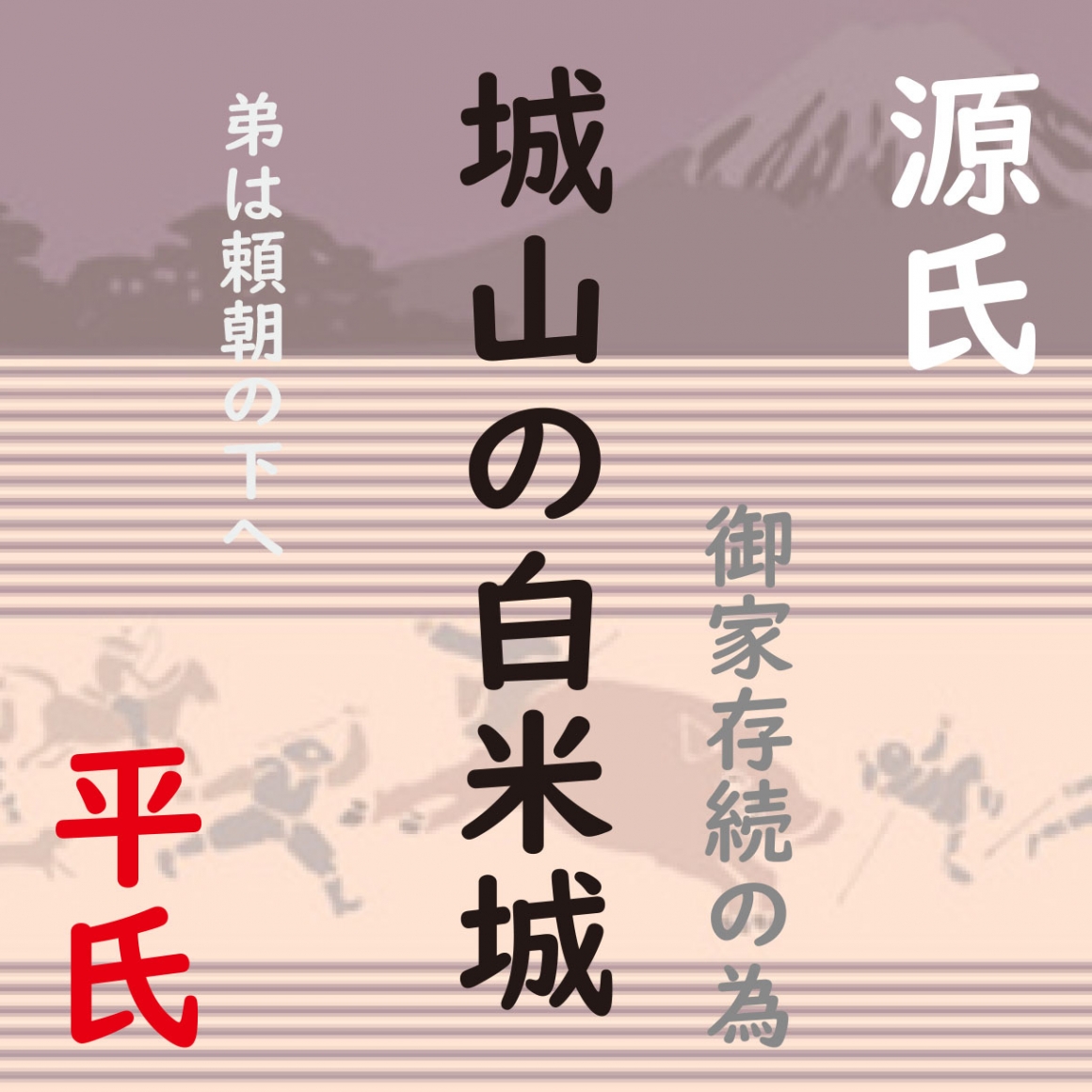
物語
Old Tale
#1146
城山の白米城
ソース場所:南アルプス市秋山 秋山遠光・光朝及び夫人の墓
●ソース元 :・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会
・ 現代語訳 吾妻鏡 五味文彦・本郷和人 編 参照
●画像撮影 : 2014年09月18日
●データ公開 : 2016年11月18日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
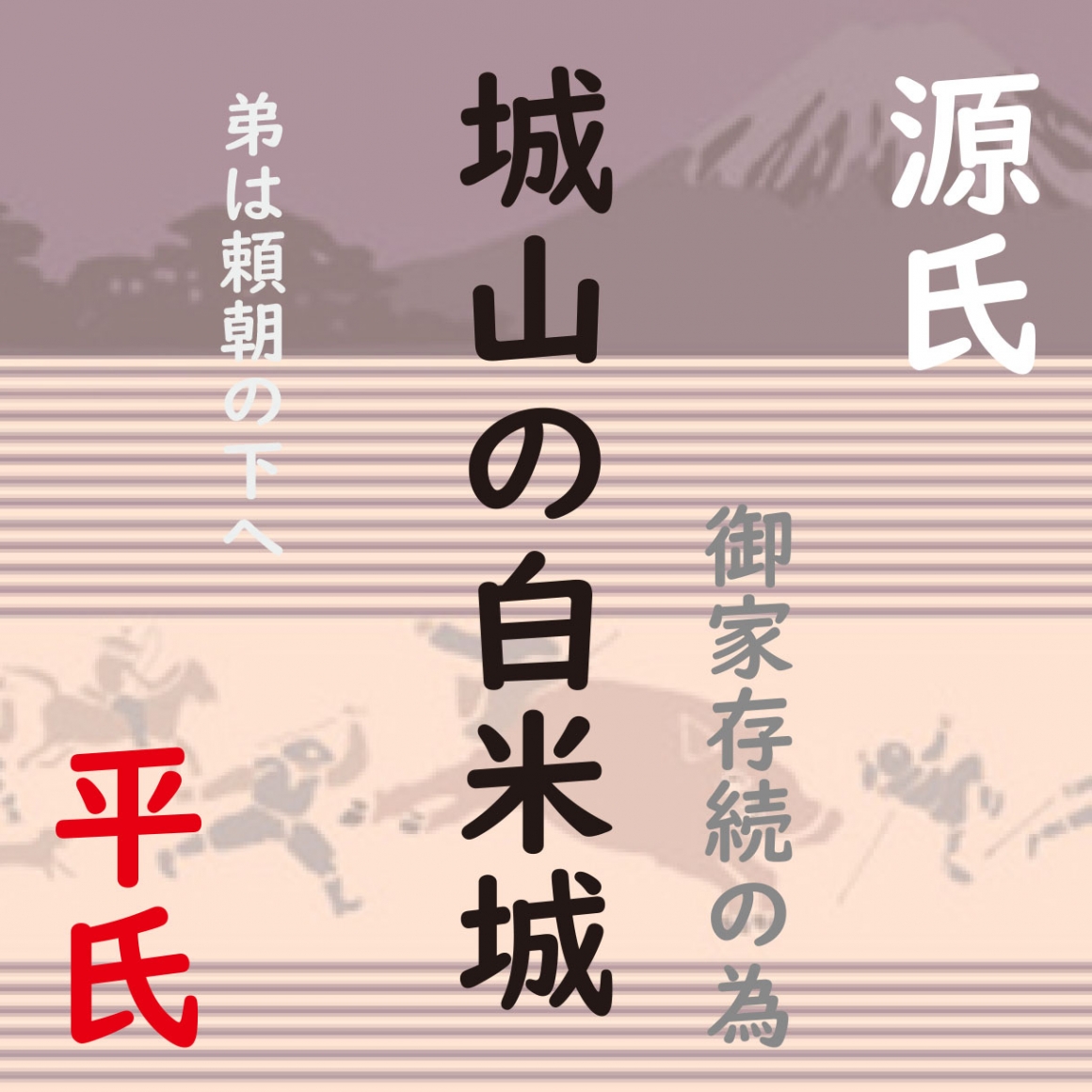
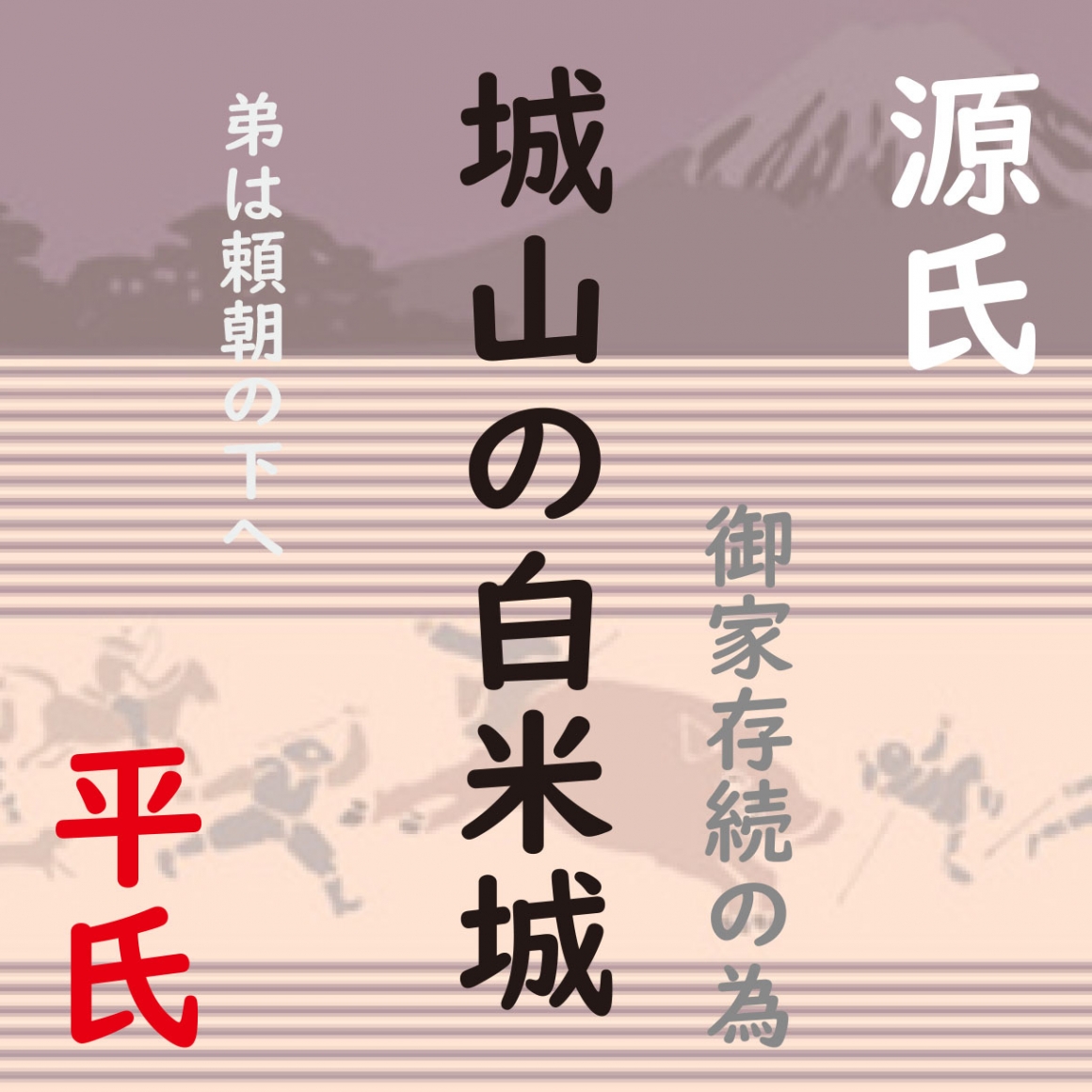
【概要】 治承四年(1180)八月 源頼朝が挙兵したころ、甲斐源氏の加賀美遠光の二人の息子、秋山光朝と加賀美長清(小笠原氏の祖)は京で平知盛の下にいました。 弟の長清は源頼朝のもとに駆け付けるため、母の病気を理由にいとまごいをしましたが許しを得ず、高橋盛綱に間に入ってもらい知盛に許しをもらい下向した。しかし、途中病を得て美濃の辺りで1,2か月を過ごし、十月十九日頼朝のもとへ駆けつけました。しかし、平清盛の長男重盛の娘を妻に迎えていた兄の秋山光朝はまだ京に居て頼朝のもとへ遅参して不信をかった。吾妻鏡(元暦元年十一月十四日に頼朝の出した手紙[元暦二年一月六日の項])に、頼朝は「伊沢信光[武田]、加賀美長清は大切にすべきだが、兄の光朝は平家についたり、木曾義仲についたりした人なので所領など与える必要が無い。」などと指示している。そして文治元年(1185)、光朝は鎌倉勢に攻め込まれ城山と言われた中野城(南アルプス市中野)もしくは中野城から峰続きの雨鳴城(南アルプス市湯沢)で自刃したと伝わる。 当時、血脈を繋ぐため、兄弟はあえて源平のそれぞれに付いたのでしょう。小笠原長清も京で大きな力を持っていた平家ではなく、挙兵したばかりの源頼朝につくのは相当躊躇し、美濃でいつまで病でいるかを煩悶していた事でしょう。運命の転機を読めた者だけが未来を手に入れて続いていくのでしょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
白米城 中巨摩郡落合村秋山
鎌倉時代、武田太郎信義の弟 加賀美次郎遠光の嫡男、秋山太郎光朝の立て籠もった城址を城山という。東も北も険しい崖で、僅かに南方から、平林村の城の橋に道が通じている。ここへ鎌倉の討手が来て城を遠巻きにした時、城内には水がまったく缺乏したが、わざと敵に見える所で、白米を盥に入れ、馬のスソをあげて、水が豊富にある如く装って見せた。敵方ではこれを怪しんで、大森何がしかの婆という者を呼んでその真相を知り、城の水源を尋ねて義丹の滝の水を断った。それでついに堪え切れず、城は落ち光朝は自害した。
附近に雨鳴山があって、雨が降る前には鳴るといい、この城を雨鳴城ともいうし、また山上に山茶花が咲くので椿ガ城ともいう由である。今も本丸、二三の郭の跡、馬冷し場などの地名が残っている。 (中巨摩郡誌 その他)
土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会
*秋山氏館跡 光朝時代の遺構は殆ど残っていないが、南アルプス市秋山の熊野神社付近が秋山氏館跡と云われ近くに「秋山遠光・光朝 及び夫人の墓」がある。 また、上記、城山は、南アルプス市中野の中野城跡、そしてその支城として、雨鳴城があり、その遺構からこの城が、大きく構えていた事がわかる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
白米城伝説とは アーカイブ1220「新府の白米城」で詳しく記載したが、この伝説は日本各地を廻る霊能者、いわゆる「歩き巫女」がそれぞれの地方へ自分の霊力を示して入り込むためのつかみに使った為、各地で同様な話がされているのではないかという説がある。県内でも各地に同様な話が残っている。(アーカイブ0518「岩殿山」、アーカイブ1146「城山の白米城」、アーカイブ0325「根古屋の白米城」、アーカイブ1220「新府の白米城」など)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。






















