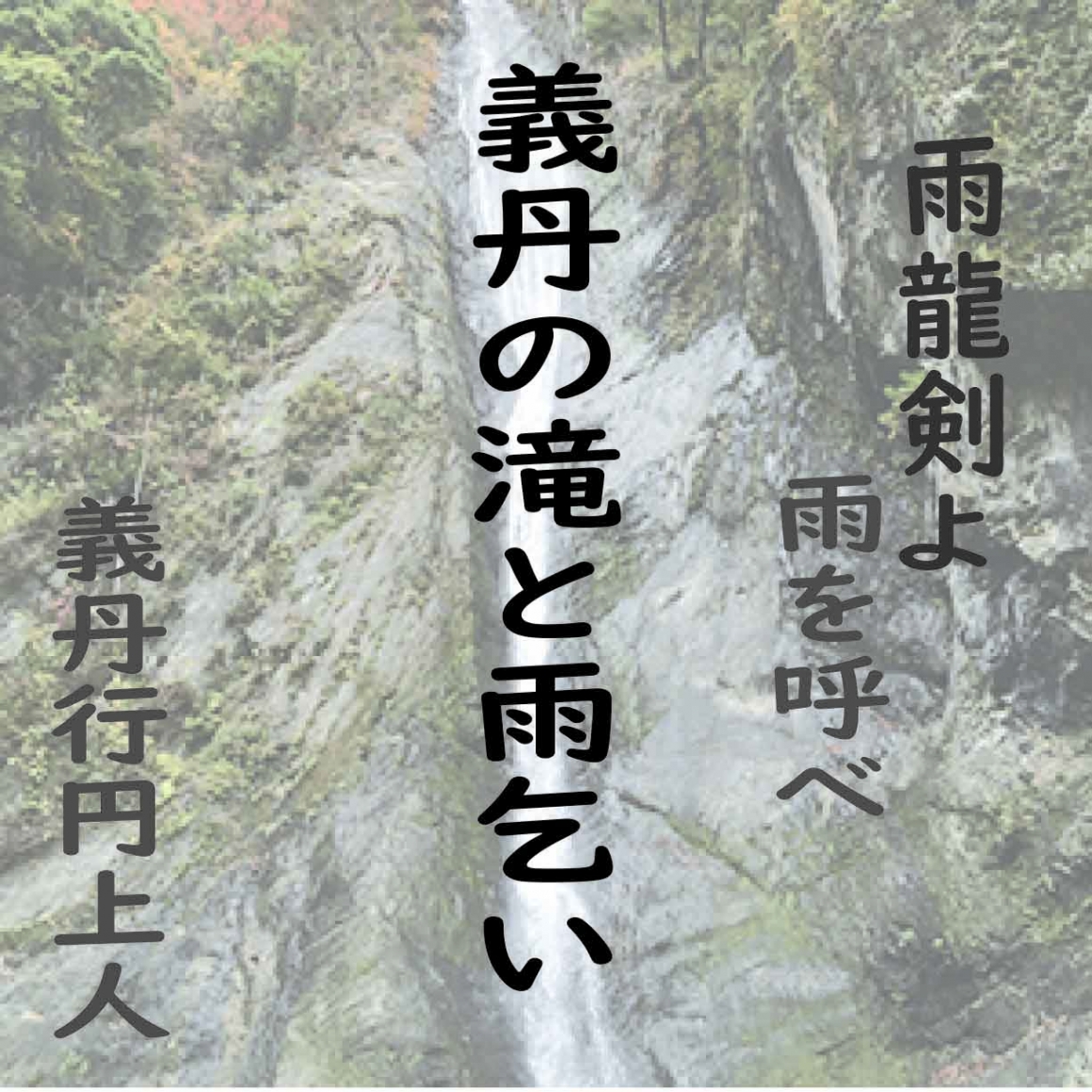
物語
Old Tale
#1163
義丹の滝と雨乞
ソース場所:南巨摩郡富士川町平林 ・ 富士川町舂米2 明王寺「雨竜剣」
●ソース元: ・土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会
●画像撮影: 201年月日
●データ公開:2017年01月05日
●提供データ:テキストデータ、jpeg
●データ利用:なし
●その他:利用に際しては許諾が必要になります。
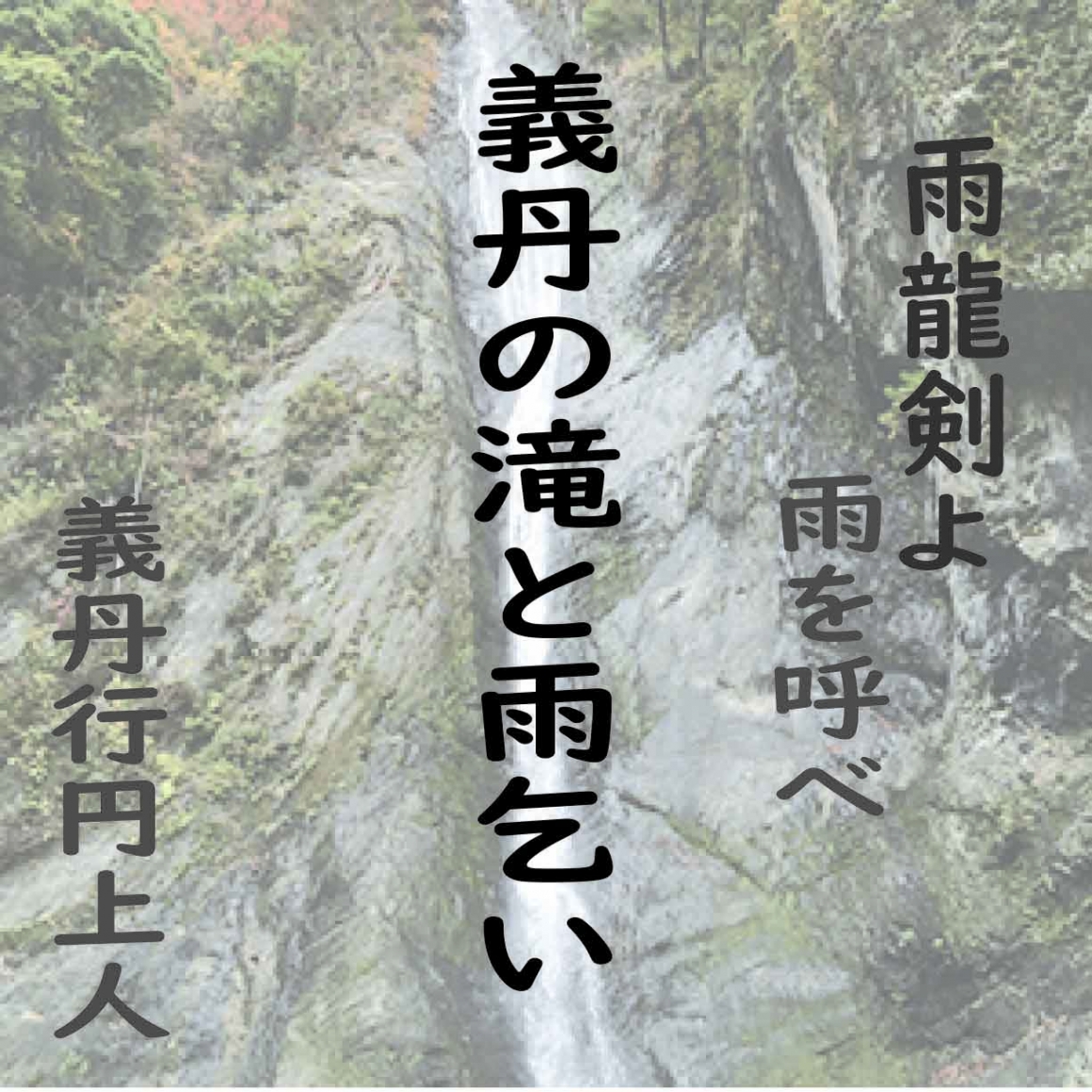
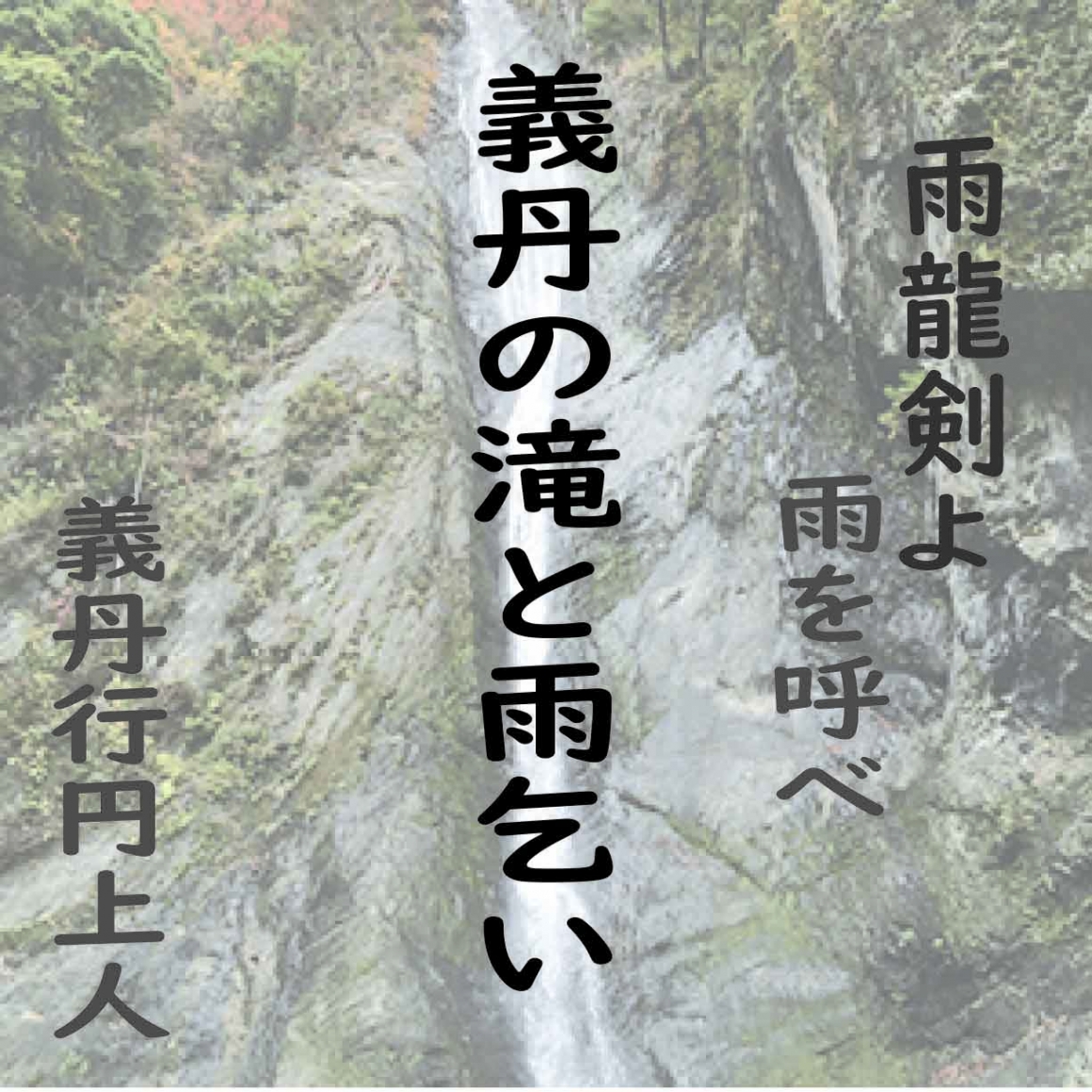
[概要] 昔、日照り続きで村人たちが苦しんでいたところへ、旅の僧が来て滝に打たれ、雨龍剣を振るい雨乞いすると雨が降り人々は喜んだ、その僧は知らぬ間に去ってしまったが、後から義丹行円上人と云う名僧と知れたので、滝に僧の名前を付け、彼の像を雨乞いの神として祀った。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
義丹の滝と雨乞 中巨摩郡平林村
戸根川の上流に高さ十数丈の滝があり、これを義丹の滝と呼んでいる。昔麓の村で、日照りが続き田の水が涸れて困っていた時一人の旅僧が来て鷹尾寺に泊まり、毎日雨乞いのためにこの滝に通った。僧は雨龍剣を天に揮い、滝のしぶきを浴びて熱心に祈ると、大雨が二日も続けて降り、田は満水となって農民は狂喜した。旅僧は知らぬ間に去って行ったが、これが駿河の義丹行円上人だと分かって、この滝の名とし、村人は上人の石像を刻んで、滝の北側の高い岩に穴を掘り、そこに雨乞いの神として安置した。毎年晩秋の頃義丹上人の祭りが行われるが、祭りの当日は必ず雨が降るといわれ、今でも日照りで困る時には農民はこの滝に集まって、雨龍剣を揮い、或は滝に入りお題目を唱えて雨乞いするが、霊験あらたかであるという。 (甲山峡水)
土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。





















