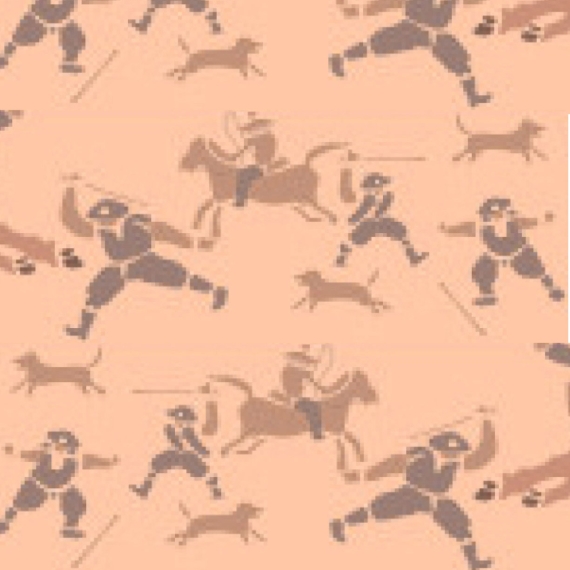物語
Old Tale
#1259
長坂駅開駅夜話
ソース場所:北杜市長坂町長坂上条 長坂駅 駅前の開駅記念碑
●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2017年10月30日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
[概要] 中央本線が韮崎駅から富士見駅(長野県)まで開通した際(明治37年)は、途中、日野春駅、小淵沢駅の二駅のみしか設けられていなかった。大正四年、当時の鉄道院が今の長坂駅付近に信号所の設置を計画。近隣の人々は信号所だけでなく、何とか駅も作ってもらい、町づくりの基盤にしようと計画した。日野春地区は駅周辺の開発に着手していたので、長坂駅の誘致まで協力することは出来ず、協力者の少ない中で地元負担金を集め、
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
長坂駅開駅夜話 (長坂上条)
日本の文明開化は鉄道に乗ってやってくる、と昔の人は言ったものです。中央線が峡北地域を貫通し、日野春駅が設置されたのは明治37年12月21日のことでした。それから年を経ること14年めにあたる、大正7年12月11日に長坂駅が開設されました。
今では、八ヶ岳山麓の交通や経済の中心地として発展している長坂駅周辺地域ですが、長坂駅ができたころはどんなだったでしょうか。
「新停車場(出来た当時の長坂駅のこと)なんちゅう所はなあ、駅ができるまで、キツネ山って言ってたもんだ。大八田のオチョンポリ山につづく、長坂上条のうっそうとした松林のおっかねえ山だ」と言われていました。そこになぜ、どうして駅ができたのか。
大正時代の長坂の人々の足跡を追ってみました。
中央線が開通して11年後の大正4年、当時の鉄道院は、鉄道の時間短縮、輸送力増強のため、駅の距離が長い日野春駅と小淵沢駅の中間点に信号所の設置を計画し、協力を長坂上条区に要請してきました。
上条区では、「信号所だけでなく、停車場もつくってほしい」と、すぐに16人による「駅設置請願委員会」を結成しました。委員会の計画は、「停車場のみでなく八ケ岳南麓13ヶ村の中心的な役割を持つ長坂のまちづくり」という大きな理想でした。
鉄道院は、この地元の願いに対し、「駅の敷地全部と工事費の一部の負担金として千円を負担する」という条件を示してきました。
請願委員が中心となり協議の結果、「区有地5,777坪を駅の全敷地に、1,500坪を道路用地として提供する」ことは何とか決まりましたが、負担金の千円の調達が大きな問題となりました。
隣の村々では、すでに開駅している日野春駅に通じる道路の新設や改良に力を注いでいる時でしたので隣村からの協力は望みが薄く、日野春村でも、村長が先頭に立って協力することもできず、長坂上条区の人々の孤独の活動が始まったのです。
工事負担金集めは、請願委員が何組かに分かれ、手分けをして歩きました。草鞋掛け、腰弁当にこうもり傘のいでたちで八ケ岳山麓の村々から、東川地(今の須玉町)、遠くは諏訪・岡谷方面までも足をのばし、泊まりがけになることもしばしばでした。こうして、3年の月日が流れました。
その間に、駅開業にむけて駅前の都市計画がつくられました。
○長坂の駅前を、八ケ岳南麓の木材、薪炭、蚕、農産物の一大集散地にする。
○駅前の右側は輸送関連業者の区域、左側は商店街の区域とし、幅8m、長さ700mの道路をつくる。
○住民から共益金を集め、その70%を共用とし、30%は停車場発展のために使用する。
これが、16人の請願委員の計画でした。
こうした孤独で長い3ヶ年の努力が実を結び、寄付金の総額は五千五百円あまりにもなりました。
世は、第一次世界大戦も終わり、大戦景気絶頂期の大正7年12月11日。
16名の熱意と努力によって長坂駅は開業しました。降りしきる雪の中、上り列車は十二時四十四分、下り列車は十二時十六分。汽笛とともに各一番列車は発車しました。
その日乗った人は93人、降りた人は98人、収入金は45円57銭でした。
それからの長坂駅前は、日本の経済の好景気とともに活気に溢れ、しだいに八ケ岳南麓一帯の経済文化の中心として発展してきました。16人の「夢のまちづくり」も、こうして軌道に乗ってきたのです。
請願委員会は、長坂駅の開業まで3年、開駅から「夢のまちづくり」に8年。合わせて11年後の大正15年12月、目的を達成して解散しました。
それからの中央線は、単線が複線になり、蒸気機関車にかわって電車が走るようになりました。走る列車の本数も増えてスピードアップされ、通勤や買い物なども大変便利になりました。
平成10年12月、長坂駅は開駅80周年を迎え盛大に記念の式典をおこない、先人に感謝するとともに町の発展をお祝いしました。
長坂駅前には、大正8年に長坂上条区の人々によって建てられた開駅記念碑が建っています。 (朝日竹夫・『長坂上条区誌』『長坂駅の本』)
長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。