


物語
Old Tale
#0515
龍宮淵
ソース場所:山梨県上野原市松留34 悉聖寺
●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会
●画像撮影 : 2014年09月08日
●データ公開 : 2016年04月01日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
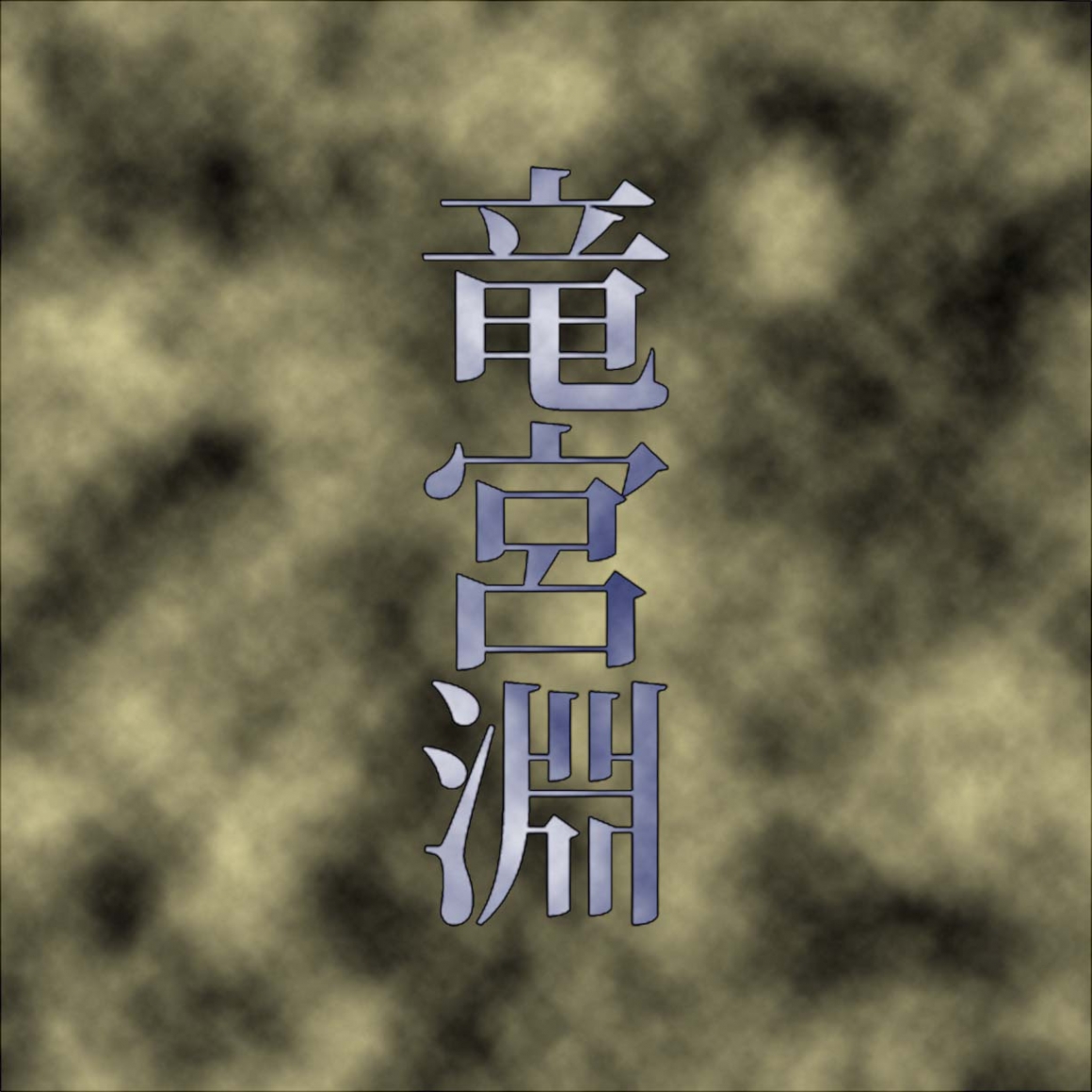
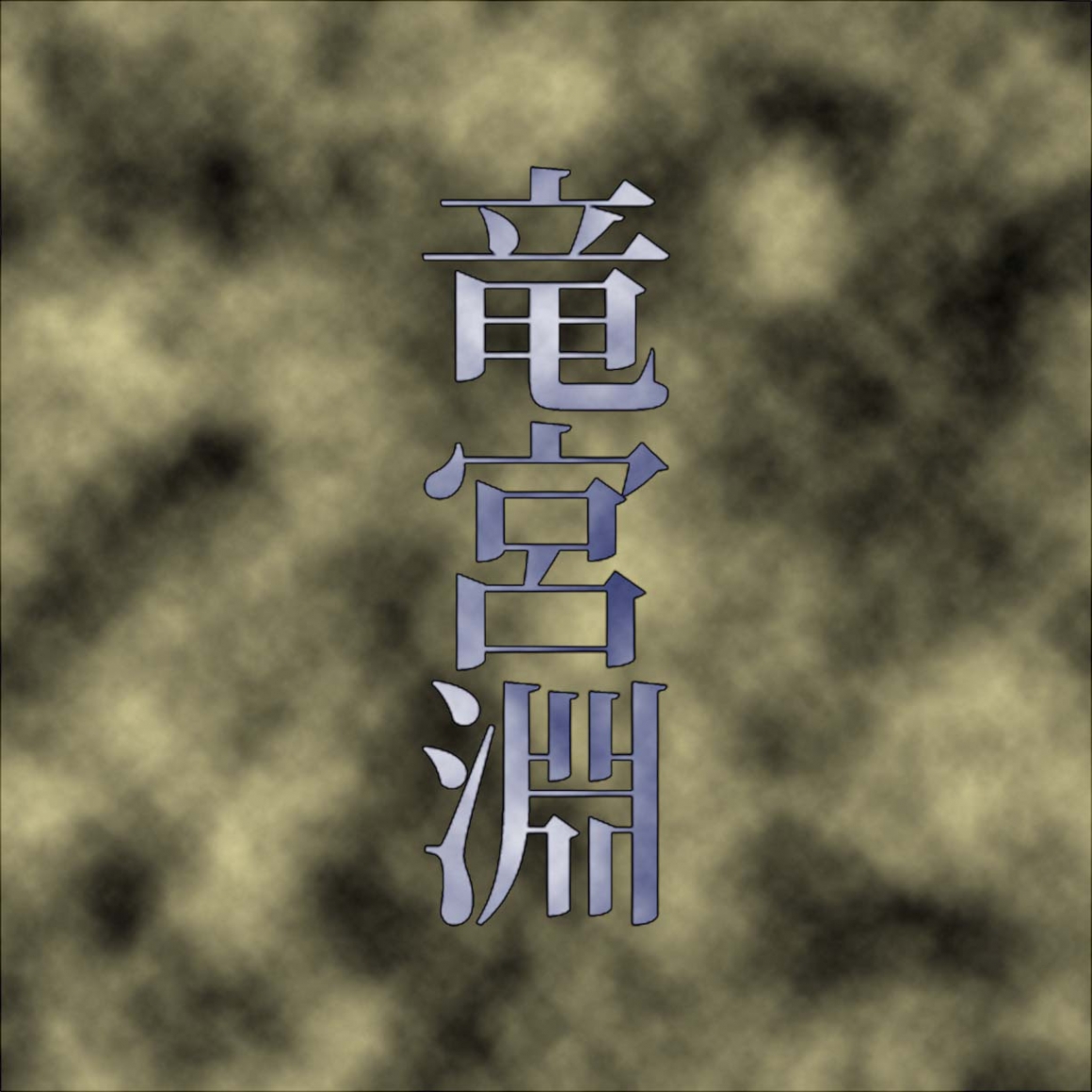






[概 要] 上野原市松留の辺り、桂川の河原が急に狭くなり渓谷を作っているところがある。ここが、名勝 杵岩や龍宮淵のある桂川峡です。 この地は、与謝野鉄幹・晶子夫妻にとっても縁ある場所で、初めてここを訪れた与謝野鉄幹がこの地を「龍門峡」と名付け、夫婦それぞれが歌に詠った景勝地です。 この中の龍宮淵にまつわるお話です。浦島太郎のようでも三つの斧のようでもあるお話です。 昔、ある百姓がこの淵の上で木を切っていて、うっかり斧と共に淵に落ちてしまった。気づくと美しい女神のような人に助けられ、水底のお城から地上に帰るときお土産を持たされた。このお土産のことは人に話したり見せてはいけない。お土産のおかげで百姓は大変豊かになったが、ある日、お土産の秘密を知られてしまい、それは石になってしまいましたとさ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
黄金の管
上野原町悉聖寺の南面を桂川が迂回し、名勝地となっている杵岩の付近に、底知れぬ淵がある。
昔、一人の百姓が、この淵の上で木を切っていたが、手元をくるわせて、斧を淵に落としてしまった。アッと思った瞬間、思わず体を乗り出したからたまらない。自分も斧を追うように真っ逆さまに淵へ落ち込んでしまった。百姓は気を失っていたが、なんだか深い深い水底へ吸い込まれるような気がしていた。どのくらいたったか分からなかったが、気がついてみると、見たこともない立派なご殿のまばゆいばかりの寝所に寝かされ、美しい女に介抱されていた。女は「ここは龍宮で、自分は一番の織り子である」と語った。
手厚い看護で百姓はたちまち元気をとりもどしたが「二、三日は体を休めた方がよい」 というすすめで竜宮の女の歓待をうけていた。だが三日もすると、女房や子供のことが気がかりとなり夢のような生活に未練があったが、いとまごいをすると、「生きてこの竜宮へ来られたのは、あなたが初めてです。竜宮があることはだれにも言つてはいけません。竜宮においでになられた確かな証拠と私との思い 出のために、私の使っていた管をさし上げます」と言って女は黄金に輝く糸管を渡した。
すると、どうしたことか急に気を失ったが、体はフワーッと浮くような感じがしていた。
気がついてみると淵の岸であった。
家にもどると、己れの三年忌のまっ最中であった。当の百姓はびっくりしたが、三年もして生きて帰って来た百姓をみた家族や親族の者もびっくりした。びっくりしている親族の前で百姓は「管を拾って来た。この管で機を織ってみろ」と言って女房に黄金の管を渡した。
女房が黄金の管を使って織り出すと管の回転は素晴しく、ひっかかって止まるようなことなく、均等にむらなく織れるし能率は上がるしで評判が高まり、機織りたちは「私もそんな管がほしい。管をどこから手に入れたか」と、しつこく聞いた。百姓は言うなと言われたが、あまり気にも止めず、「竜宮に行けば管が手に入る」と話した。すると管は一瞬にして石ころと化してしまった。
しかし女房は、梭(ひ)の中で横糸を自在に繰り出す管の形と仕組みをよく覚えていた。細工師に頼んで同じ形のものを堅木で作らせた。
すると細工師は管をどんどん作り、機織りの家に売った。こうして上野原は織物の生産が群を抜いて高まり、名産地として全国に知られるまでになった。
(注) 管=織機の部分品。梭に入れ横糸を送り出す器具。
内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。


















