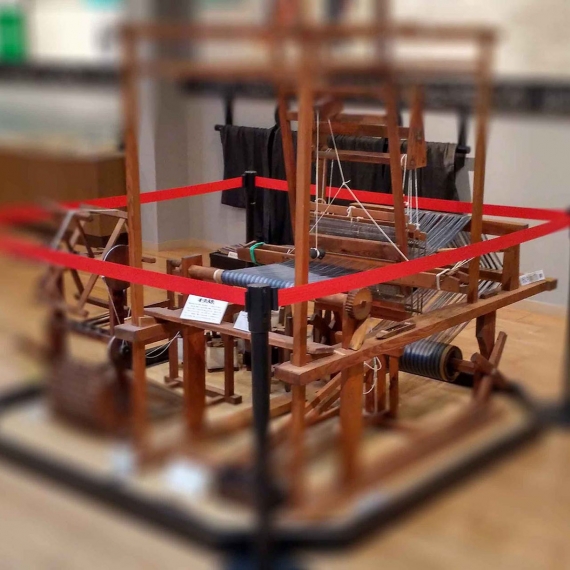物語
Old Tale
#1514
蜘蛛ン淵
ソース場所:南巨摩郡身延町下部清澤
●ソース元 :・ 土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2018年06月25日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。








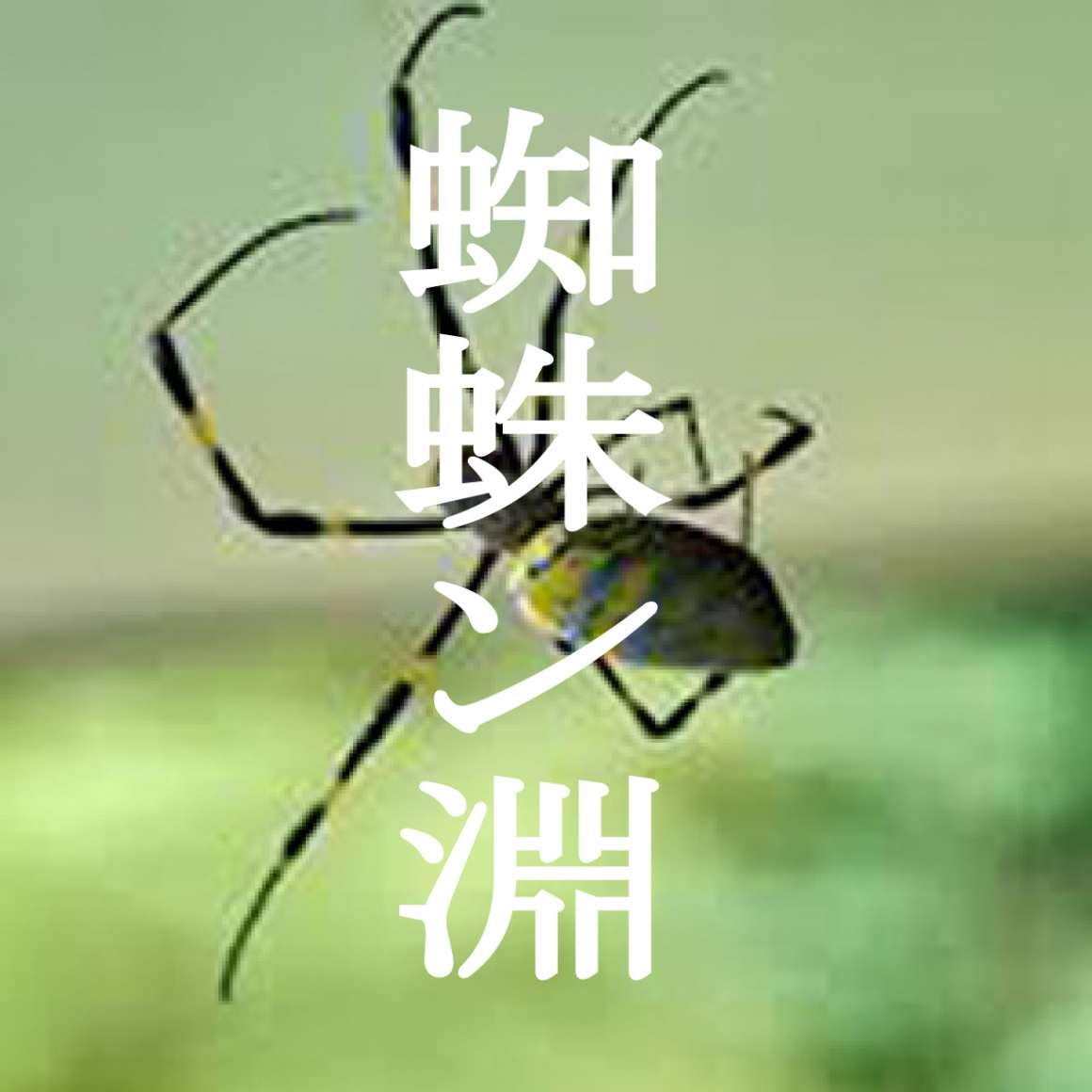
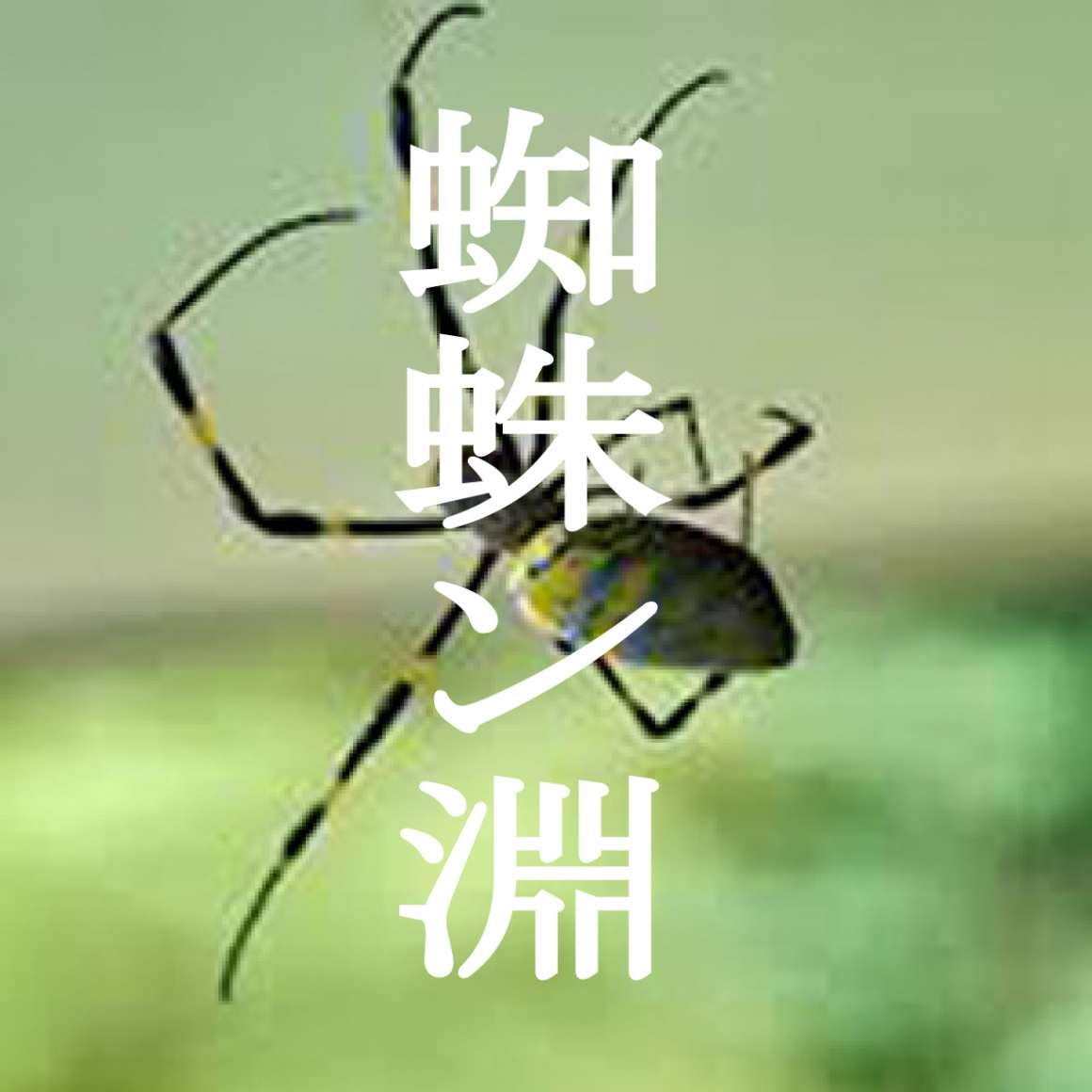
「概要」 雨乞いの儀式が行われる場所は聖地として、普段から近づいたり。殺生を嫌がられたりしている。この淵にも、不思議なお話が。「不用意に釣りなどしていると、蜘蛛がそっと近づいてきて、何回も何回も漁師の足に糸を付けていく。蜘蛛の糸に気付かず、糸を外さないままだと、いきなりものすごい力で淵の奥底へ引きずり込まれますよ。淵へは近寄らないことが何よりでございましょう。」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
蜘蛛ン淵
下部温泉の渓谷に蜘蛛ン淵という淵がある。或夕方一人の漁師がこの淵に釣をしていると、傍の樹上から大きな蜘蛛が下ってきて、漁師の足に糸をつけてどこかへ行った。蜘蛛は数回やって来て同じことを繰り返すので、漁師も変に思って、数条の蜘蛛の糸を足から外し、傍の枯れ木にそれを移して様子を見ていた。暫くすると、淵の底からヨーシという声が聞こえて、蜘蛛の糸を引っ掛けた枯れ丸太は、物凄い地響きと共に淵の中へ引き込まれ、漁師は辛うじて難を免れた。それ以来この淵を蜘蛛ン淵と呼び、今も五尺余りの鯉が棲んでいるという。 (峡南の伝説)
土橋里木(昭和28年)「甲斐傳説集」山梨民俗の会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下部川に合流する雨河内川を3キロ程遡ると川の名は「金白沢」と変わる。この沢をさらに遡ると大きな滝があり、その滝下が大きな淵になっている。ここが下部の雨乞い淵で、周囲の集落其々に雨乞いの場所や儀式があるが、その効き目がない時は、下部の各集落が一緒になってここに集まり、雨乞いをする習わしがあり、雨乞い以外で近づいてはならない淵とされていた。
この淵が「蜘蛛ン淵」と呼ばれるようになったという。
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。