


物語
Old Tale
#1521
神代餅
ソース場所:日野春駅
●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2018年06月27日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。


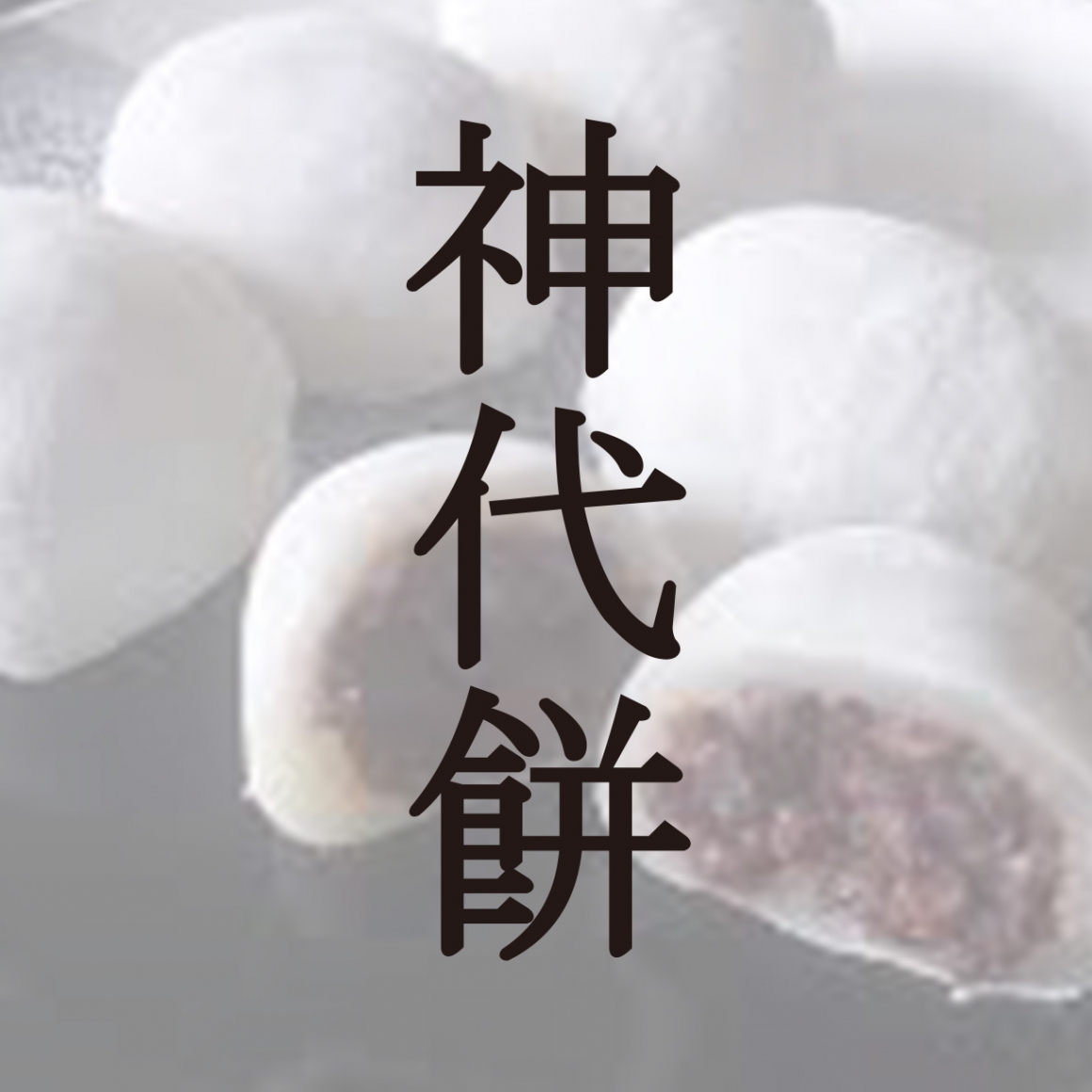
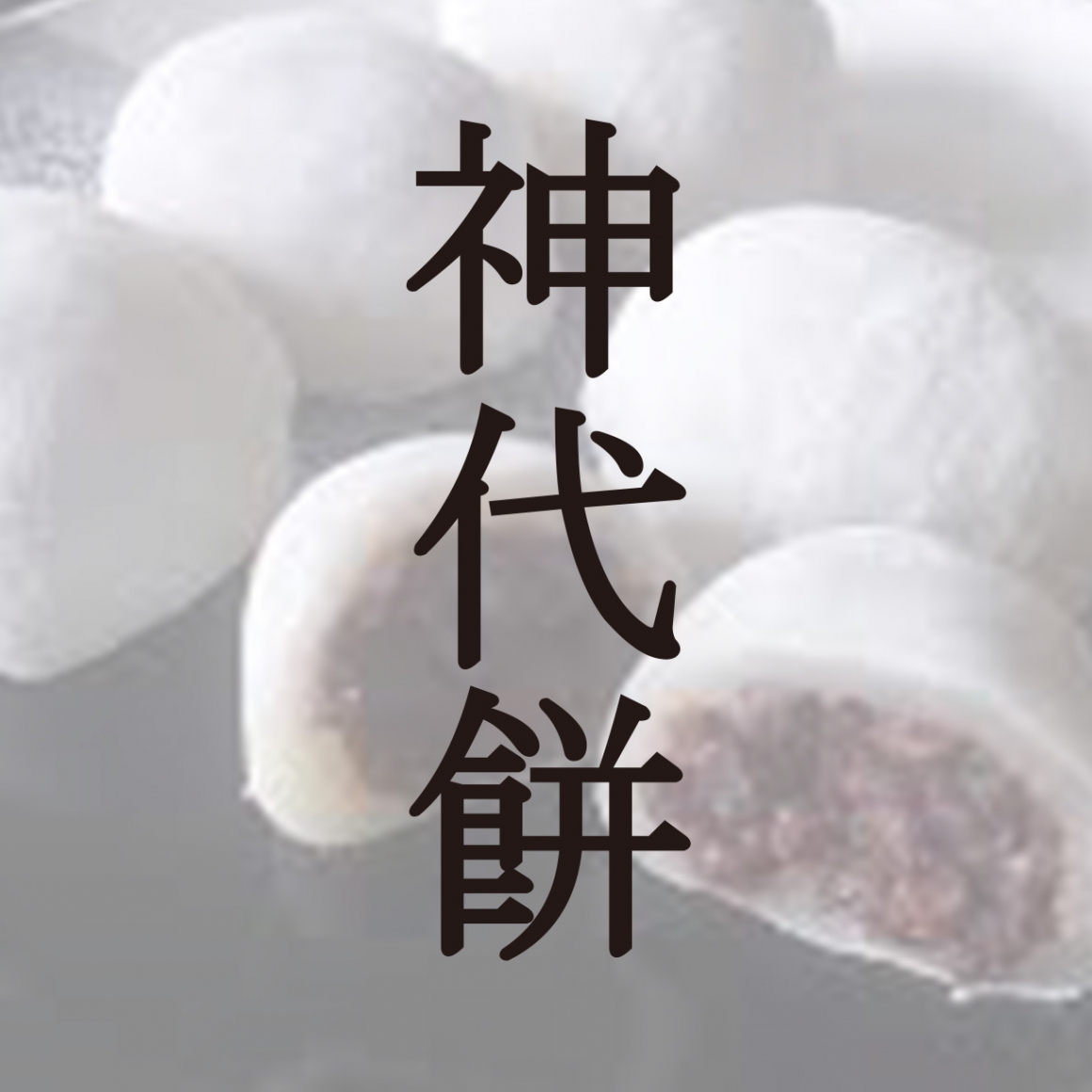


[概要]
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
神代餅 (富岡)
日野春駅ができたのは、明治37年のことです。
その後、長坂駅ができるまでは、八ヶ岳南麓の、長坂、高根、大泉地域の玄関口として大切な役割を果たすとともに、南アルプスの登山口として発達してきました。
その日野春駅には、珍しいものが二つありました。
ひとつは、当時走っていた蒸気機関車に給水をするための給水塔です。
あとの一つは、”神代餅” という餅まんじゅうのホームでの販売です。
蒸気機関車に引かれた列車は、韮崎から八ヶ岳の台地にかかると急にのろくなり、いかにも苦しそうにあえぎあえぎ登っていきました。列車が日野春駅に着くころには、甲府で給水した蒸気機関車を動かすためのタンクの水も残り少なくなってしまいます。ですから、日野春駅に到着した下り列車は必ずここで給水をしなければなりませんでした。
給水塔につながれた太いホースを通して蒸気機関車のタンクに勢いよく水が入っていきます。給水には、20分ぐらいかかりました。
「ジンダイモチー・・・、ジンダイモチー・・・。神代餅はいかがですか」
いつからか、日野春駅のホームでこんな売り子の声が聞かれるようになりました。
20分間の停車時間を利用して何かできないかと考えたアイデアです。
「神代餅」という名前は、南アルプスのふもと武川村の実相寺にある神代桜にあやかってつけられました。直径3cmぐらいの大きさで粒餡の入った餅が10個、経木にまかれ神代桜の絵を描いた包装紙に包まれて売られていました。値段は、一包10銭、安くてうまいとたちまち沿線の名物になりました。
この神代餅も、太平洋戦争が起きると、砂糖や米などの材料が手に入りにくくなり、製造も中止されてしまいました。
そして、給水塔も昭和39年ごろから中央線に電気機関車が走るようになるとその役割を終えて使われなくなりました。
いま、日野春駅ホームのはずれには、給水塔がポツンと取り残されています。また、神代餅をつくるのに使われた石うすは、長坂町郷土資料館に展示され、昔の日野春駅の繁栄のなごりを伝えています。 (細田令次)
長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。
























