


物語
Old Tale
#1567
雷の撥(かみなりのばち)
ソース場所:甲斐国一宮 浅間神社 笛吹市一宮町一ノ宮1684
●ソース元 :・ 甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 (参照 2024-08-27)
●画像撮影 : 2015年07月02日
●データ公開 : 2020年08月27日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
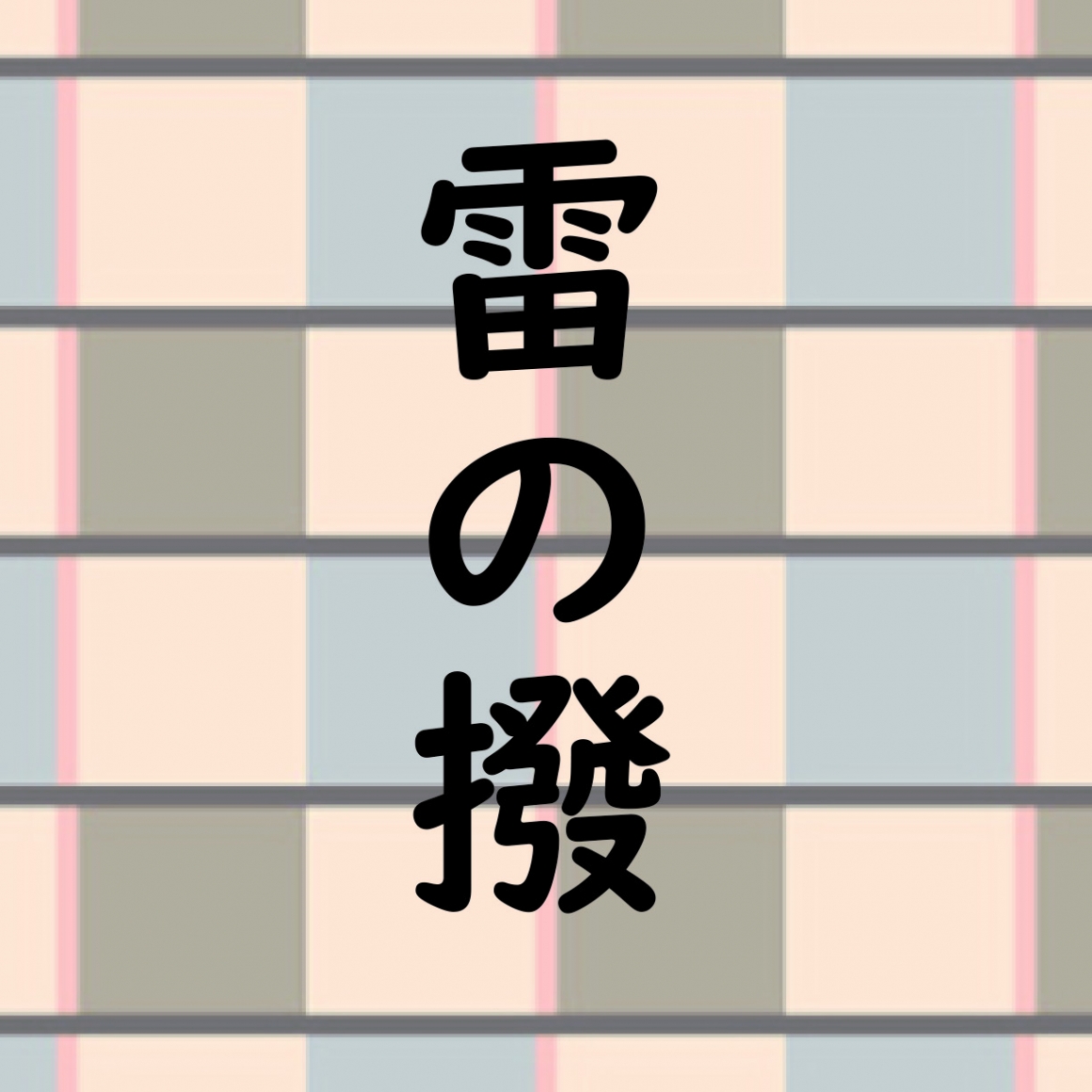
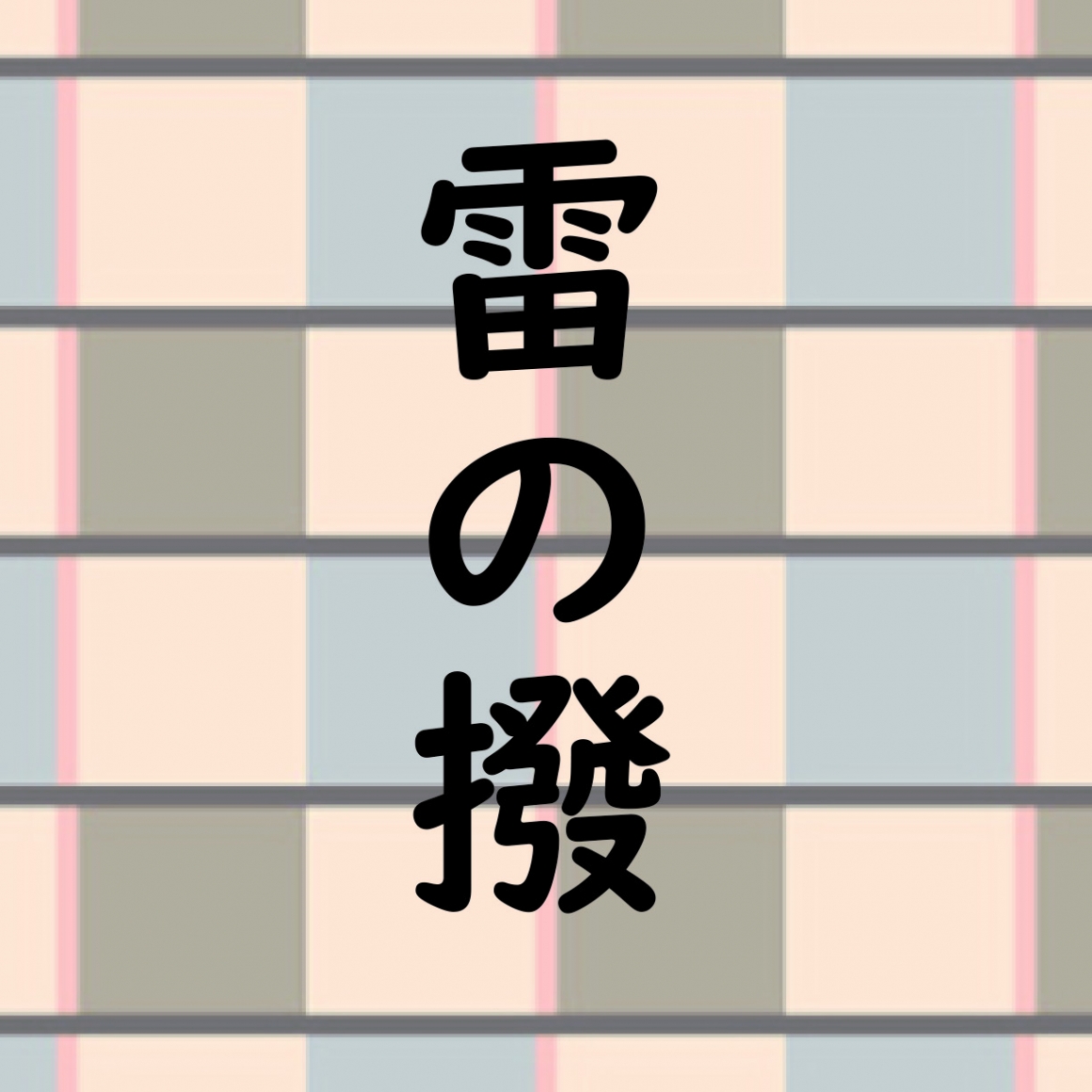




[概要] 江戸時代の甲斐の国の様子を「裏見寒話」と名付け、客観的に書き残した野田成方 宅に、一宮浅間神社の宮司がやって来て、神社の寺宝について語る。それは「雷の撥」なのだという。もしお調子者から聞き取りをしたなら与太話にしかならないような話なのだが、当時のインテリである宮司から、それがどの様な場所で発見されたのかとか、別地方で寺宝とされている撥の形状や、そこで後日、雷雨後に届けられた撥と前から寺宝とされていたものが同様だったというような伝聞も含め、怪しき話も論理的に採話している様子がわかる。今の一宮浅間神社の霊宝としてはお話が聞こえてこないが、どこかにそっとしまわれていたら見てみたいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
雷の撥 (甲斐国一宮 浅間神社 笛吹市一宮町一ノ宮1684)
一ノ宮神職の古屋宮内が家に来て神社の霊宝について話してくれた。
木や石ではなく、太鼓のバチの形をした物が、雷の落ちた跡に有ったという。雷斧 等のたぐいか。
こんな話も聞いた。上州藤岡村にある寺で、ある年この寺の本尊を開帳した。その時、他の霊宝も披露されたが、その中に「雷撥」と云う物があり、その形は普通の太鼓のバチの形で、両端は少し太くて水晶のようだ。長さ 二尺。これは以前、白雨の晴れた跡に落ちていたものを拾った人が寺に納めたという。その後、また、白雨迅雷の後、同じような形のものを拾った人が寺に納めに来た。再度落ちたのか?と宝蔵を開いてみれば、元の撥が有り、それと並べてみると長さも径も違わなかったので、二つで一対として寺宝にしている。雷雨後に落ちていたのだから、これは雷鳴を鳴らすための物でしょう。
「裏見寒話」 巻之五 古跡並びに名木 の項より
【裏見寒話とは、野田成方が甲府勤番士として在任していた享保九年~宝暦三年(1724-1753)までの30年間に見聞きしたり、調べた甲斐の国の地理、風俗、言い伝えなどをまとめたものです。只々聞いたものを記すだけでなく、言い伝えられている某氏の名前を古い書物から探し出したり、例えば鳥の羽が夜光ることを、不思議な話だと記すだけではなく、闇夜に猫の毛を逆立てると火花が散るがこういった現象ではないだろうか?と考察している。当時の様子や、一般の人達にとって常識だった歴史上の事柄(歌舞伎や浄瑠璃などで演じられ、当時の庶民に良く知られていいた)を知ることが出来る。】
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。


















