


物語
Old Tale
#0526
忍野八海
ソース場所:忍野村忍草
●ソース元 :・ 内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
・ 忍野村忍草の東圓寺HP、各種科学雑誌またはNEC社史など参照
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2016年04月01日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
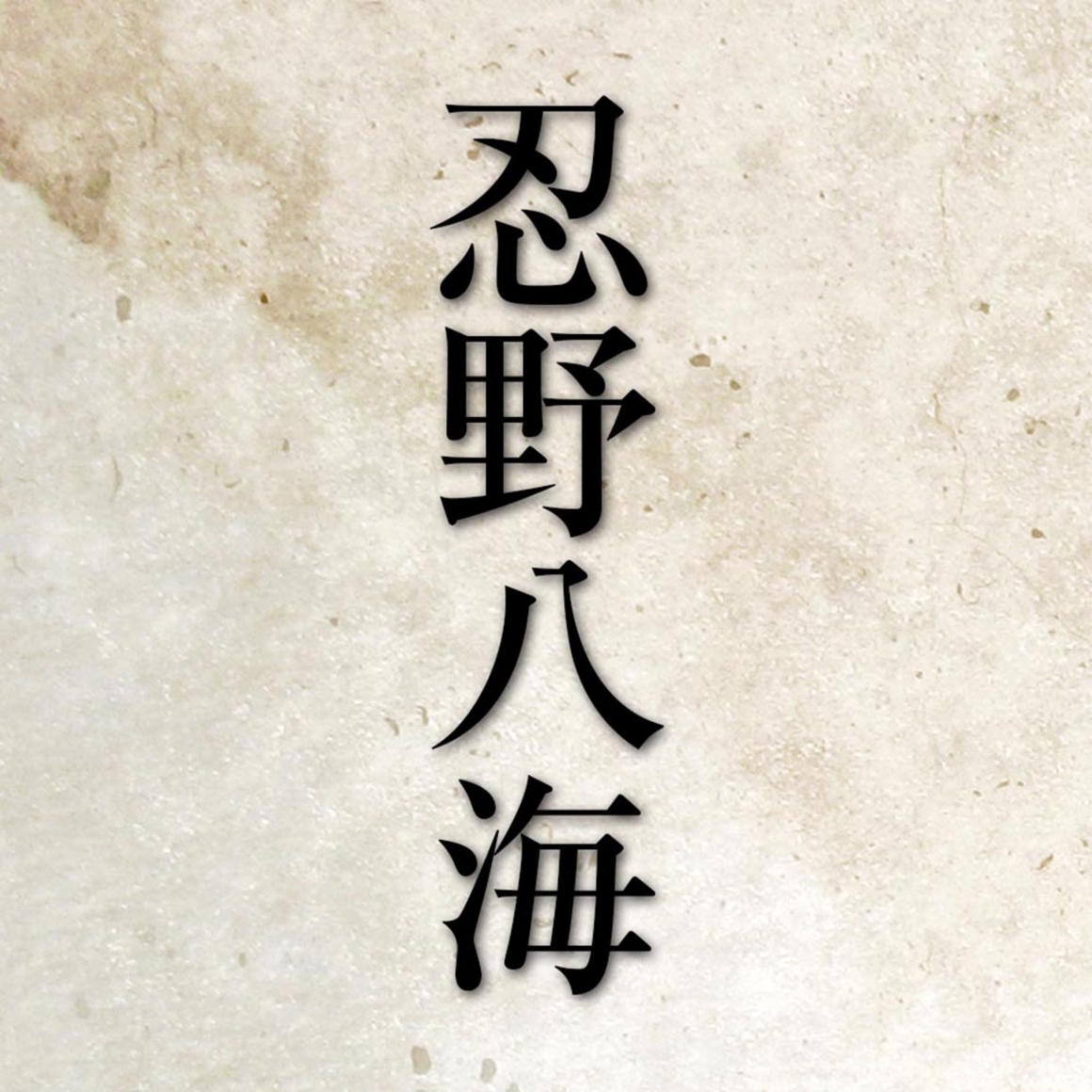
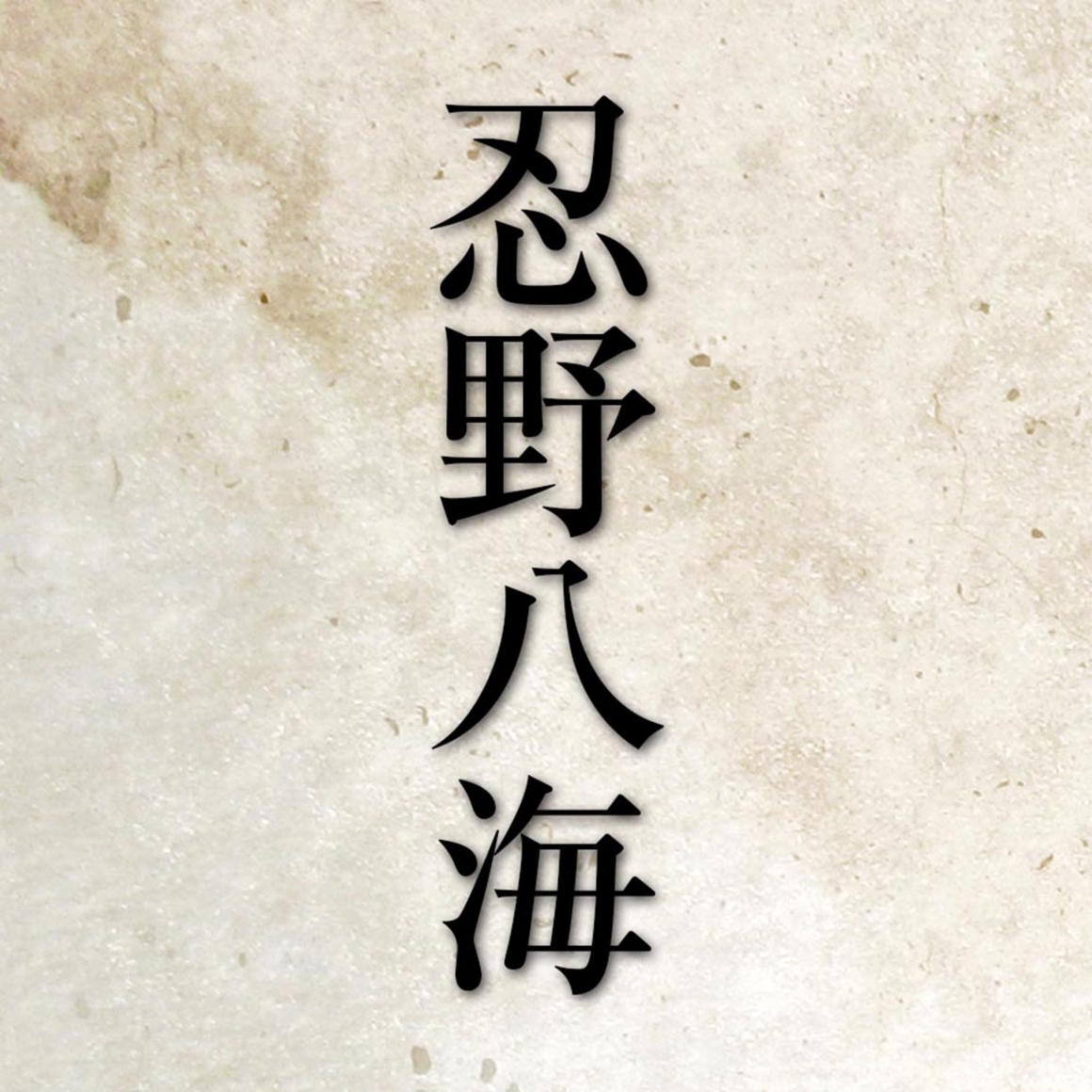
[概 要] 忍野八海 忍野村には忍野八海といって、八つの池があり、それぞれに伝説がある。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
忍野八海
忍野村には忍野八海といって、八つの池があり、それぞれに伝説がある。これはそのうちの二つである。
〈濁り池〉
ある日、富士で修験の苦行を重ね装束は破れ、ひげも髪もぼうぼうに伸びて、見るからに見すぼらしい行者が八海の一つ、今は濁り池と名付けられている池のほとりの家を訪ね、出てきた老婆に「のどのかわきをいやしたい。水を一杯いただけないか」と所望した。ところが、うさんくさそうな顔をして見ていた老婆は、水をくみに行っている間に物でも盗られてはかなわぬとでも思ったのか「この池の水は、濁り水で飲み水にはできない」とうそを言って断った。行者はほんのしばらくの間老婆をあわれげに見ていたが、何やらとなえると立ち去って行った。やれやれと、老婆が水をくもうと池に行くと、何と池の水は濁り水に変わっていた。
後に旅の行者は富士で修行を重ね神通力を身につけた行者と分かり、老婆は「人を分け隔てするな」という教えと悟って、富士を礼拝し深く悔い改めた。その心が通じたのか、濁り水であっても器にくみとれば、またもとの清水になるようになった。
〈御釜池〉
大昔、池のほとりに美しい姉妹が住んでいた。その池の主は、大きな蟇(がま)であった。大蟇はいつも池に連れ立って洗濯にくる姉妹のうち、妹にいつしか心震える想いを抱くようになってしまった。
姉妹が池のほとりに現れるのを待っていては池から顔を出し、口をパクパクさせて結婚の申し込みをしたが、カエルの言葉がわかるはずもない姉妹には、大口をあける大蟇が怖くてならず、棒を振り回したり石を投げたりして交代で洗濯をし、大蟇を近づけようとしなかった。
どのような仕草をしても意が通じぬどころか、かえってますます邪けんにされるので、想いの丈を例えるならば、深い深い千尋の谷よりもなお深く恋こがれた大蟇であったが、とうとう求婚を断られたと悟り、このうえは強引に我が物にせんと、姉が棒を持ち妹が洗濯をしているところを、すきをねらって妹に飛びつき、池の中に引き込んだ。姉の悲鳴でかけつけた近所の者もどうすることも
できなかった。
こんなできごとも、いつか遠い話となり、大蟇池はいつかお釜池と名を変えた。
(注) 忍野八海 = 富士信仰身祓場として富士元八湖といわれる。濁り池、御釜池、鐘池、出口池、銚子池、底抜池、湧池、菖蒲池の八つの池をいう。
内藤恭義(平成3年)「郡内の民話」 なまよみ出版
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
忍野八海(旧根元八湖霊場)が有名になったきっかけは、天保の大飢饉にありました。普段から寒冷で肥沃とは言えない忍野村は、多くの村人が亡くなり、離散するしかないような状況でした。当時この地域は谷村代官所(都留市)な管轄でしたが、郡内一揆の影響で混乱していたので、忍野の村役たちは市川大門の代官所へ直訴したそうです。
そこで忍野村を救済するために、市川大門の大寄友右衛門という豪農が、当時流行の富士講のような事業をしようと考えました。
それは忍野の数ある湧水のうち八つを選び、それぞれに八大竜王をお祀りし、各池に和歌を記した竜王碑を置き、池を巡りながらお経のように和歌を詠みあげるといった霊場巡りです。当時の日本人は自然の雄大さの中に心の拠り所を求め祈ることを大切にし、また祈りの場に行くことを愉しみとしていました。そこで大寄の考えた八つの池を霊場としてまわるという、今でいう観光事業のようなシステムは大当たりしました。その観光事業により忍野の人たちは救われました。(このことについては、忍野村忍草の東圓寺HPに詳しく記されています)
忍野八海の湧き水は、富士山の雪解け水が長い時間をかけ伏流水となりわきだしてきたものです。この水は、実は宇宙にも運ばれているのです。
忍野八海の湧水は、1983年8月スペースシャトル「チャレンジャー」号に持ち込まれ「無重力下で雪の結晶を作る」実験に用いられました。(詳しくは各種科学雑誌またはNEC社史などに記載されています)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。


















