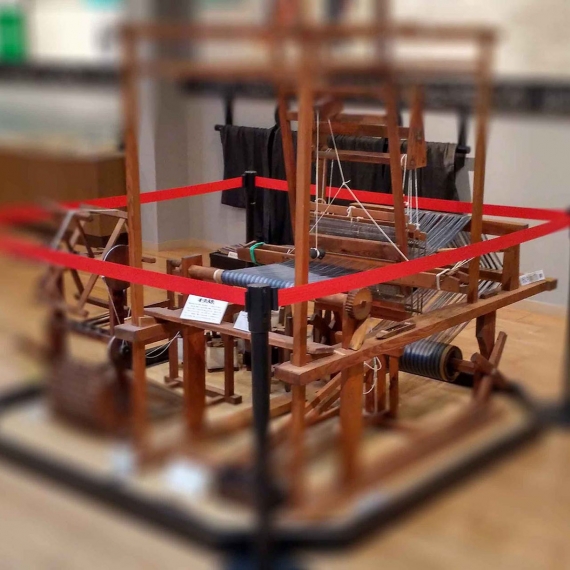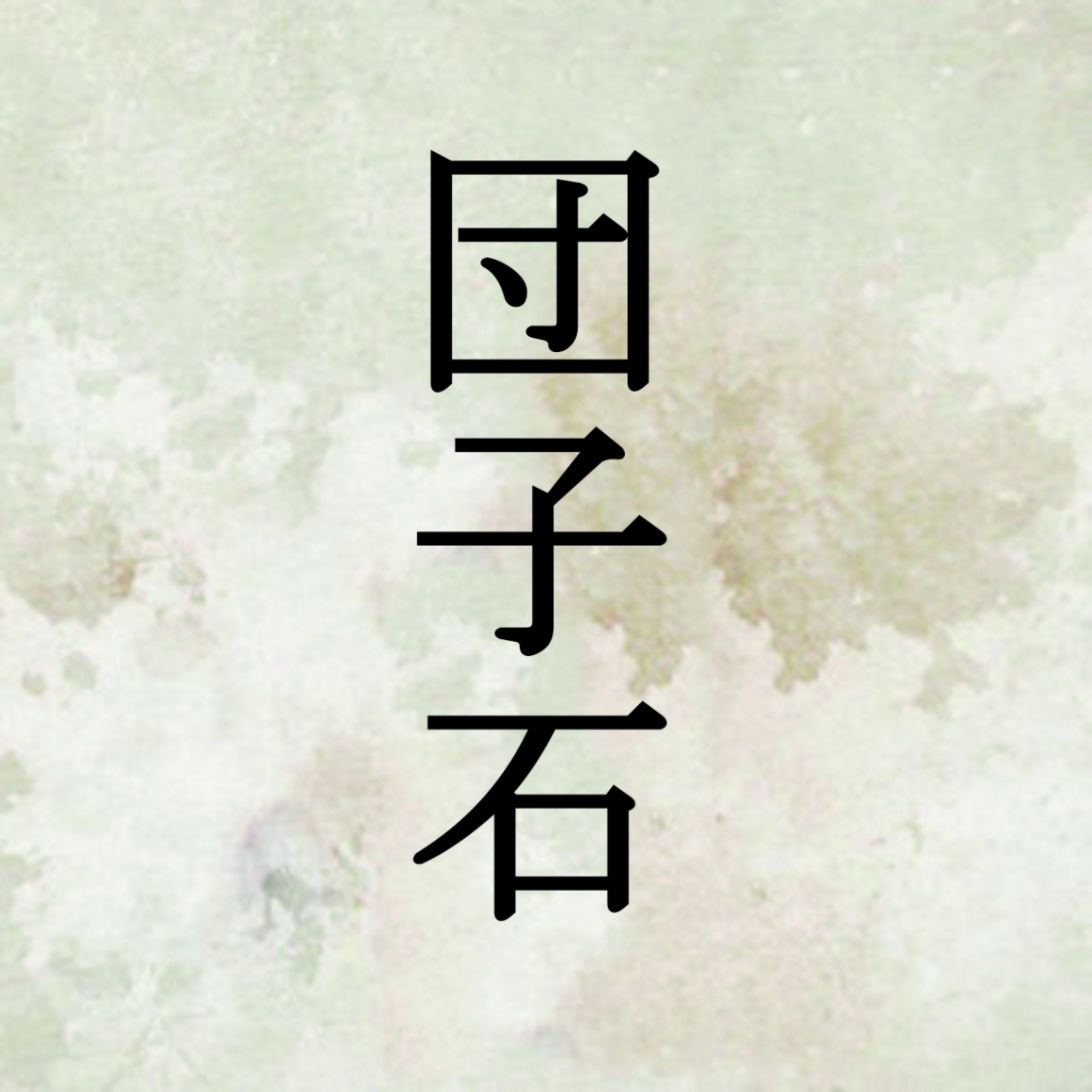
物語
Old Tale
#0547
団子石
ソース場所:甲斐市団子新居字団子石
●ソース元 :・ 山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」
・ 甲斐志料集成3(昭和7-10年) 甲斐志料刊行会 編 (甲斐志料刊行会 編『甲斐志料集成』3,甲斐志料刊行会,昭和7至10. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1240842 )
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2016年06月24日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
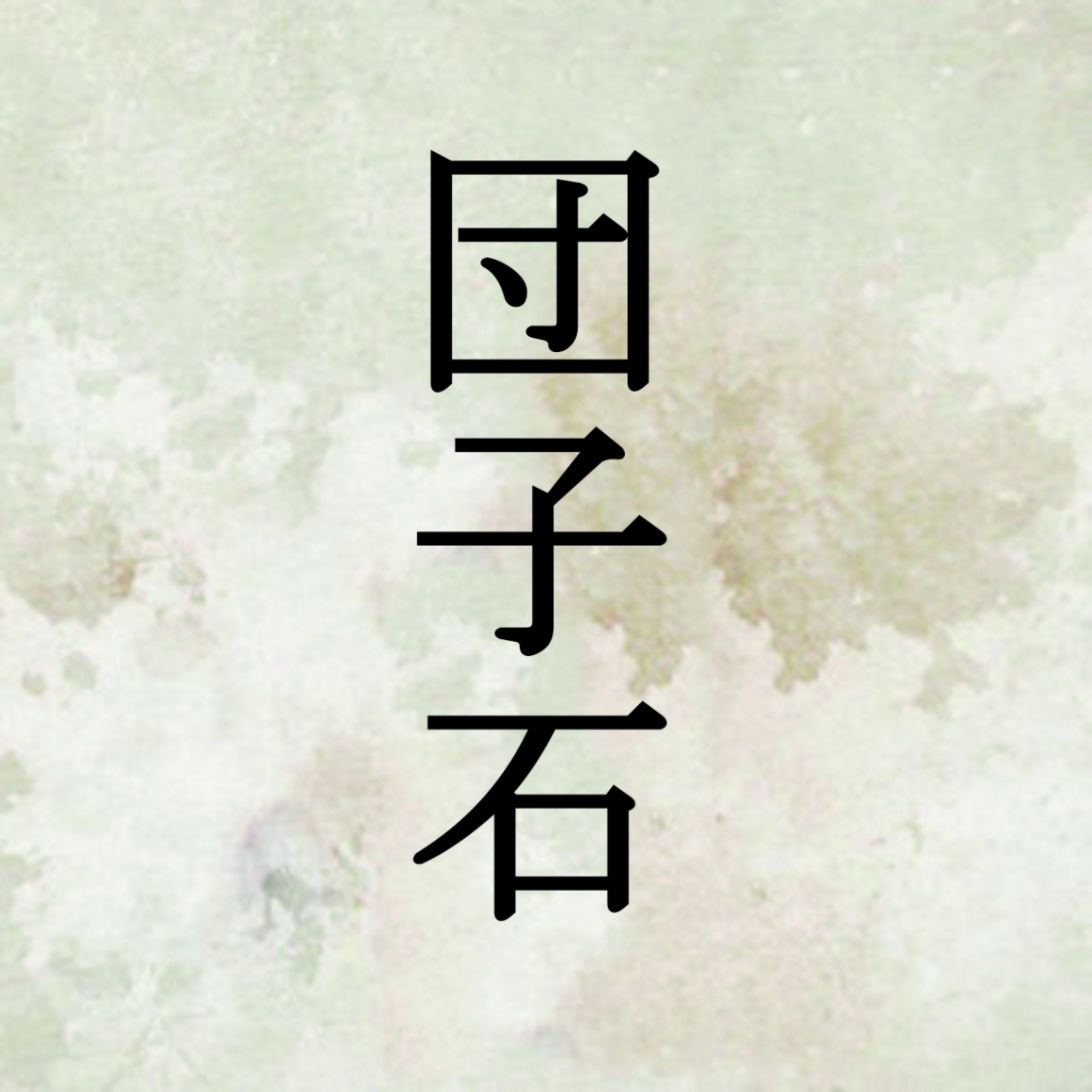
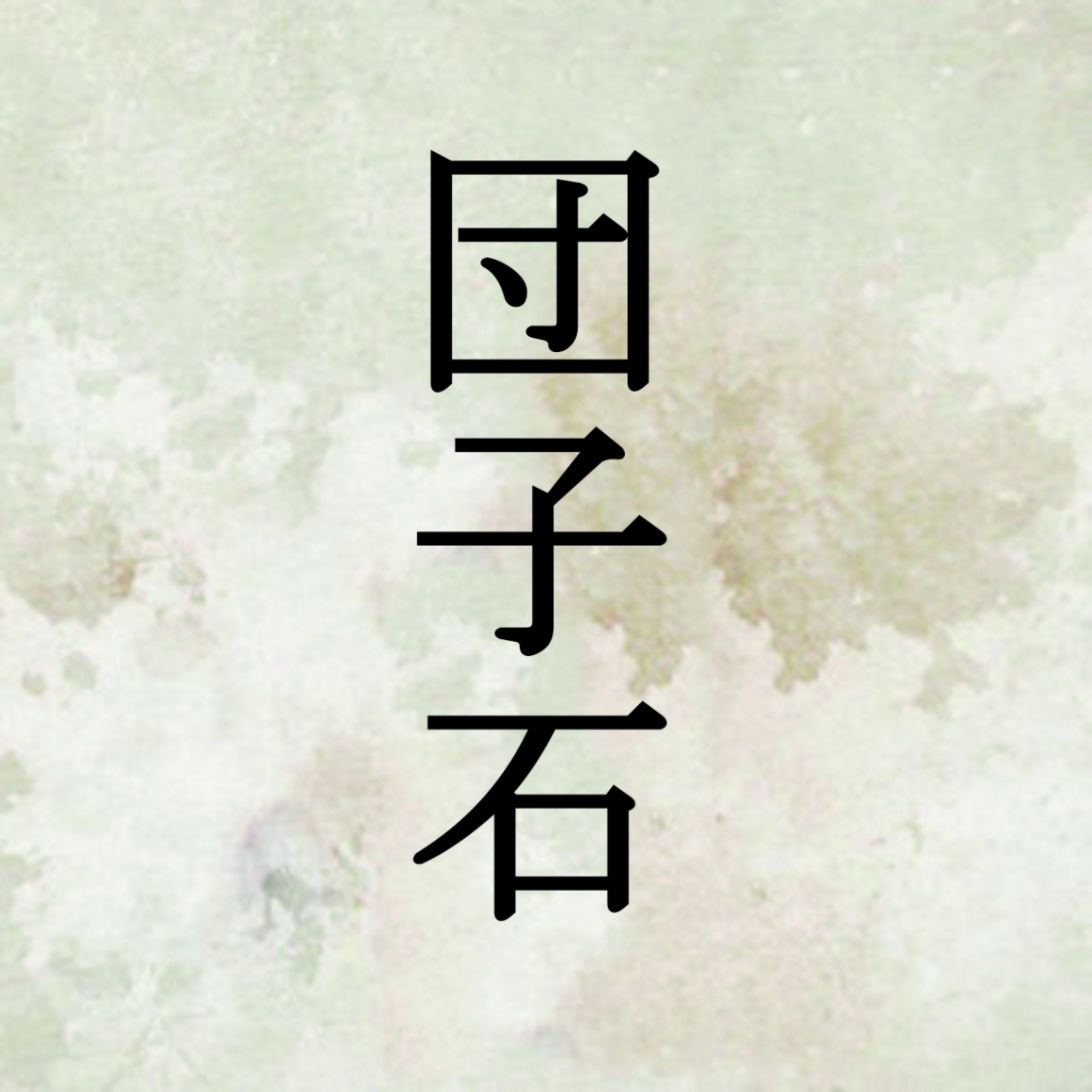
【概要】 甲斐市団子新居周辺で時折みつけられる「団子石」。 直径1~2cm程の球状の火山性石。 外側がきな粉のような黄色がかった茶色で、その中は黒っぽく、素材感も外側とはちょっと違う。ちょうどあんこの入ったキビ団子のような石。 この石には欲張りなおばあさんと弘法大師とのお話が伝わっている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
団子石
むかしむかし、弘法大師という偉いお坊さんが、国じゅうを修業しながら旅をしていました。たまたま茅ケ岳の麓を通ると、山中で一人の老婆が団子を売っていました。長旅でおなかをすかせていた大師は思わず老婆に声をかけて「修業しながら、旅から旅とまわる身ですが、食べる物もなく、大変ひもじい思いをしています。どうか、そのお団子を少し恵んではくださらぬか」といいました。
ところがこの老婆がたいへんな欲張りで、「これは石の団子でたべられない」と言って大師へのお布施をすげなくことわってしまいました。大師は老婆の強欲を哀れみ、その心根を正すため、じゅずをサラサラと押しもんで経文を唱えたところ、団子はほんとうの石に変わってしまったといいます。
今も村奥の山中から、外側は黄色で中にあんこのような石の入ったかたまりが出て、村人はこれを団子石と呼んでいます。またこの石がたくさんあるところから団子と呼ぶ集落さえあります。 (双葉町)
山梨県連合婦人会 編集・発行(平成元年)「ふるさとやまなしの民話」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
江戸時代、甲府勤番士として30年間在任した野田成方が記した裏見寒話にはこのように記されています。
団子新居の団子石(北山筋団子新居村)
この奥の山に、木欒子[モクレンジ:ムクロジの事]程の土の塊があり、これを割ってみると中に小豆の餡に似た物が入っていて、まるで団子のようだ。
昔、空海がここを通った時、老婆がきなこ団子を食べていた。空海がそれを乞うと、老婆はケチで「これは食べ物ではありません。土の塊です。」と言う。空海は怒って加持祈祷すると、団子は土塊になった。また、この村の渓流は白水である。これは昔、炊し水を流した跡という。 (「裏見寒話」 巻之五 古跡 並びに 名木 の項より)
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。