


物語
Old Tale
#1237
送り犬
ソース場所:北杜市
●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
●画像撮影 : 201年月日
●データ公開 : 2017年10月17日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
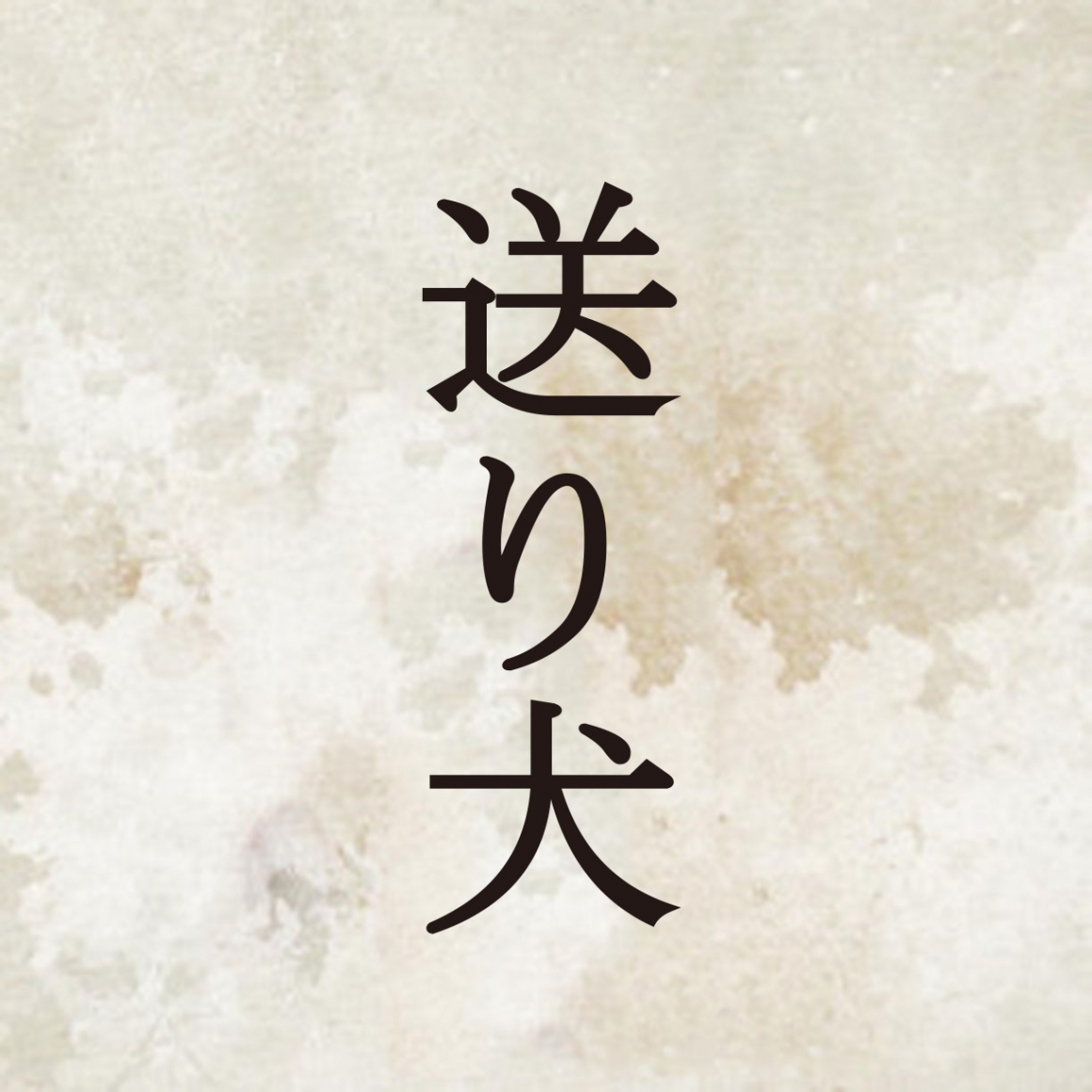
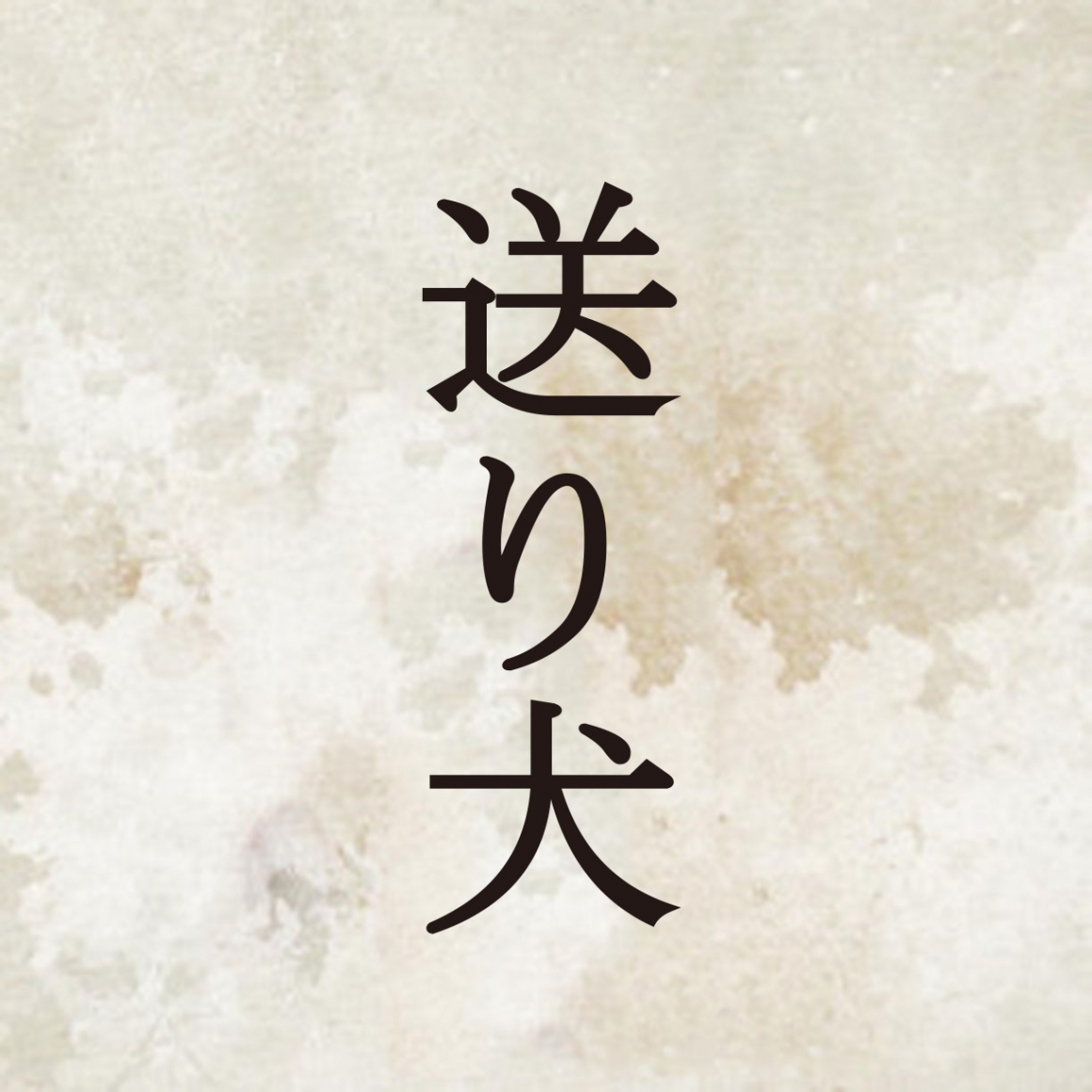


[概要] 日本から「ニホンオオカミ」が消えた。街中で「野良犬」を見かける事もほとんどなくなった。その野良犬達が里山と獣たちが棲む「ヤマ」の間で人から離れ生活しているのを「山犬」と呼んだ。 まだオオカミが夜の山道に出没していた頃、山犬も人間にとっては油断できない動物だった。ただ、オオカミと違って山犬は少し人間に対して友好的だった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〔白州の民話・伝説〕送り犬 横手
昔、横手のある婆さんが、日暮れて中山峠の道を、家に帰ってきました。すると火のような目を光らせた山犬が、あとになり先になりついてきました。ときには足に絡みつきそうなまでに側にきました。
婆さんは、こわくて、こわくてたまらないが、誰も助けてくれる人はいないので、うしろを見たり、ころんだりすると、たちまち犬にかみ殺されますから、気をつけて、やっと、自分の家までたどりつきました。山犬もはなれずに来て、戸間口にすわっています。
婆さんは急いで、飯一杯盛って出し「どうもご苦労様でごいした」と、礼をいうと山犬はそれを食べて、帰って行ったといいます。
世間では「送り犬」とか「送り狼」などといって、よく山犬に出あったようです。目が暗やみに強く光るので、タバコの火と間違えて「火を一つお借しなって」といって、きせるを出し、かみつかれた人もあったそうです。(古老談)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
棒道の送り犬 (小荒間)
① 明治の初年ころ、小池忠衛門は中馬追いを業として、谷戸村と信州上諏訪間を往来していた。春は主として食塩を、夏から冬にかけては綿、さつまいも、しょうが、魚類などを馬の背をかりて諏訪へ運び、諏訪からは春は播き大豆、味噌大豆を、秋から冬へかけて米を甲州へ運んだ。
この中馬追いには、本業とするものと農業のよかにするものとの差はあるが、ほとんど村内全部のようにこれをやったものだ。いずれも馬二、三頭をもち、小泉村小荒間から立沢を経て上諏訪に至る棒道を、雨の日といわず、風の日といわず通ったものである。
ある日、忠衛門はいつものように米をつけて、上諏訪からの帰途立沢まで来ると、秋の日はとっぷりくれてしまった。花戸ヶ原にさしかかると名物の送り犬につかれた。賽の河原も淋しく過ぎて小荒間の人家が近くなったから安心して後ろを見たら犬はいなかった。小荒間の村屋を出はずれたら、また山犬がついて来た。谷戸村大芦の入り口の鳩川の橋のたもとで、「ごくろうよう」といったら、犬は姿をかくした。この送り犬は、人がころぶとかみつくというので、中馬追いは夜道となると非常に用心深く歩いたものだ。また腰には沓切りといって小さい鎌を忘れなかった。
これは護身用とともに火打ち石を失った時に、これで火を起こすのである。火を見ると山犬はすぐに逃げたそうだ。
② 明治二、三年ころ、商用で上諏訪へ行った帰りの瀬戸左一郎は、立沢まで来ると、後ろから急いで来た井出清助と道連れとなった。二人は道連れの出来たのを喜びながら、花戸ケ原にさしかかった時、左一郎は松の大枝をかついで清助にもかつぐことをすすめた。
小深沢までくると、例の送り犬がやみから眼を光らして二人を送った。二人は沓切り鎌で石を打ち、火を起こして先に用意してきた松の大枝を燃やしはじめた。すると送り犬はどこかへ姿をかくしてしまったということである。
③ 中島幸左衛門が、やはり花戸ヶ原の中ほどまで来ると、一匹の送り犬が中馬追いの姿を見ると道の真ん中までのそのそと出て来て、懇願するように幾度か頭をさげる風情をして大きく口を開いた。度胸のよい幸左衛門が犬の口の中をのぞいて見ると、小さな骨が口の奥に刺さっていたので、手を入れてそれを取ってやった。すると、その犬は非常に喜んで尾を振り頭を下げて森深くへ立ち去った。
幾日かの後に中馬追いの幸左衛門が花戸ヶ原にさしかかると、前に助けてやった犬が出て来て、彼のたもとの端をくわえて引っ張るので、犬のなすままに道の小脇のヤブのかげまで行った。しばらくすると闇の中からざわさわという物音が聞こえてきた。気味わるく思って耳をそばだて、ヤブのかげからすかしてみると、それはオオカミの大群が過ぎ行くのであった。この大群に出会ったら、それこそ命はあぶなかったであろう。幸左衛門は「畜生でも恩をおぼえていたか」とひとり言をいった。オオカミの大群が行き過ぎてしまうと、その犬はくわえていたたもとの端をはなした。 (『長坂町誌』)
長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。






















