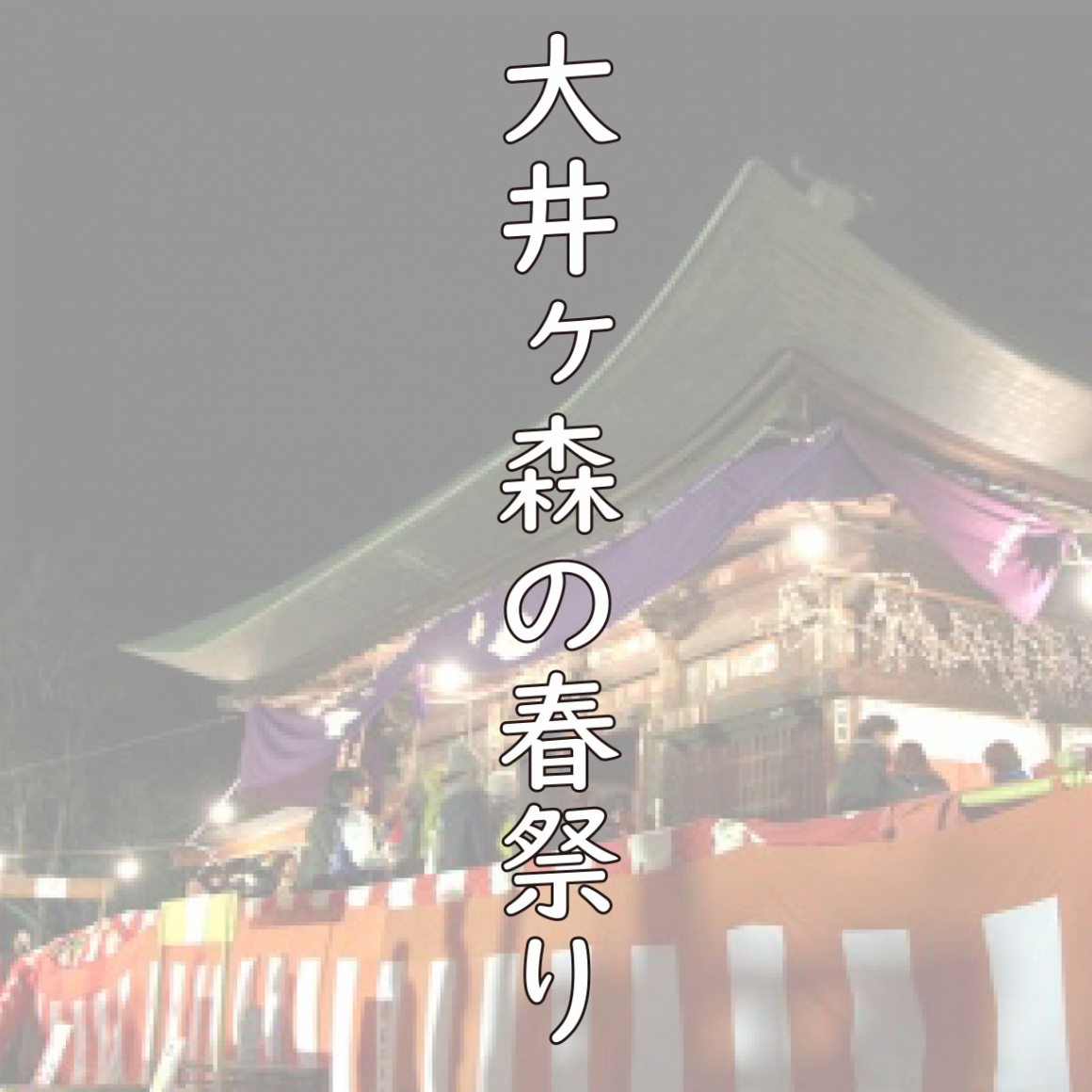
物語
Old Tale
#0577
大井ヶ森の春祭り
ソース場所:北杜市長坂町大井ヶ森1278
●ソース元 :・ 長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
●画像撮影 : 2015年11月03日
●データ公開 : 2016年06月24日
●提供データ : テキストデータ、JPEG
●データ利用 : なし
●その他 : デザインソースの利用に際しては許諾が必要になります。
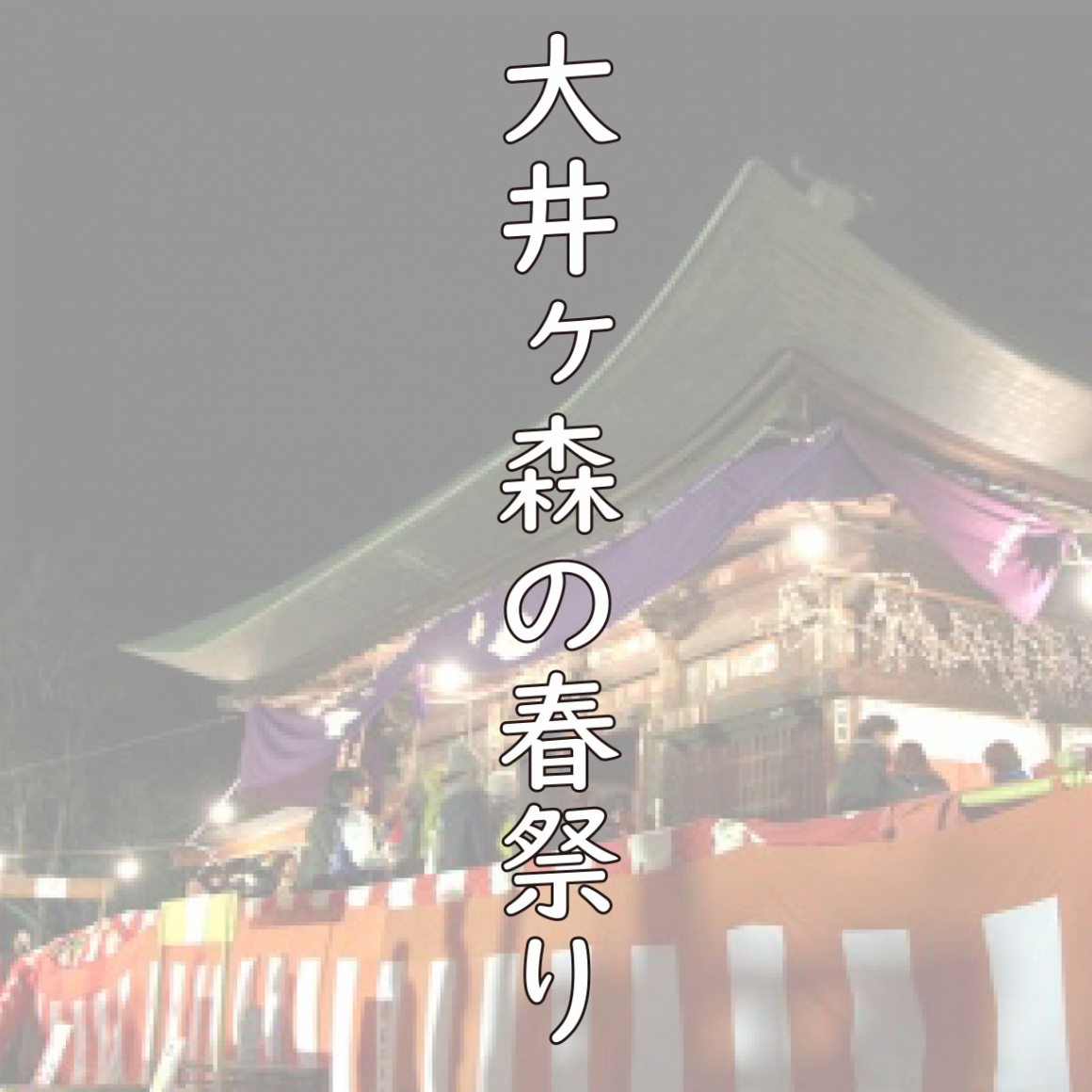
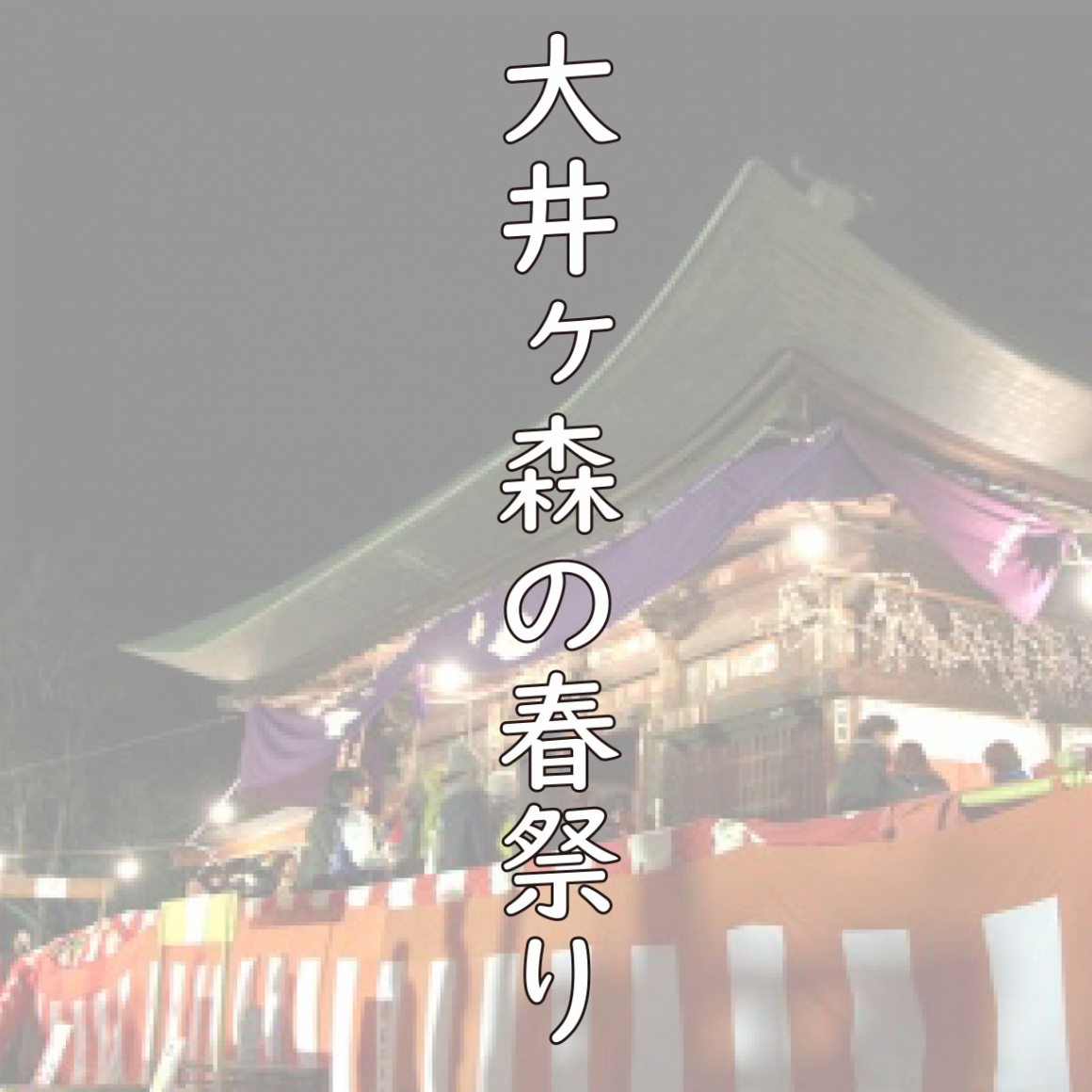
[概 要] 北杜市長坂町大井ヶ森にある大井ヶ森聖観音堂(旧 西方寺跡)の境内には船に乗った御地蔵さん「岩船地蔵」が祀られています。この地蔵尊は、下野の国(今の栃木県)の岩船山高勝寺を起点とした踊念仏地蔵尊で、佐久地方を経てこの地に流行してきた信仰の対象です。鉦や太鼓を打ち鳴らし、船に乗せた地蔵尊を担ぎ、近郷の村へ順々に送っていくことにより、「西方浄土」への旅立ちをイメージする御利益があったそうです。地蔵尊には「享保四年 大井ヶ森 施主 善男女百三人」と刻まれています。この地で大層な賑わいのあるお寺だったのでしょう。戦前まで、龍岸寺の僧侶たちにより、春の祭典が行われ賑わいを見せていたそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大井ヶ森の春祭り (大井ヶ森)
春祭りの季節になると大般若を思い出す。
祭日の3月28日には、観音堂前の道路端には露店が並び子供たちを待っていた。子供たちは、店をまわっては好きなものを買い、祭り当番の家でつくってきた白いやわらかい団子をもらって食べるのが楽しみだった。
小さい観音堂の中では、6人のお坊さんがご本尊の前に積まれた六百巻の大般若の経本の前に座り、その後ろには村の役員さんと祭り当番が座っていた。観音堂に入りきれない村人たちはお堂の前で、中の様子をうかがいながら祭典の始まるのを待っていた。やがて、鐘の音を合図に「・・・ダイハンニャー・・・」の読経が始まると、お坊さんたちは積まれた経本を次々に取り上げて、アコーディオンをひくようにバラバラと両手で開いては閉じる動作を繰り返した。そのあと、中に座っている役員さんたち一人ひとりの頭の上で同じことが繰り返された。開いた経本が閉じられるたびに経本の間の空気がさっと回りにはじかれ、前に座っている人の頭の上に注がれた。
やがて、お坊さんたちは観音堂の縁側に出て外に立っている人たちの頭上でも同じことを繰り返した。子供たちもお坊さんの前に進み出て一人一人頭を下げて風を受けた。
していることの意味はわからなかったが、ただ「パラパラ・・・、サー」という音とともに頭の上に落ちてくる風の感触はいまも記憶に残っている。
後になって聞いた話であるが、これは邪気を払い無病息災を祈るとともに、子供たちの肝の虫を追い払うためだという。
一時間ほどのこうした祭典が終わると、観音堂の中には祭り当番がつくってきた肴が並ぴ、酒が出された。子供たちは、お目当ての団子をもらうと、それを食べながらお堂の前に並んだ露店を回り歩いた。
夕方近く、六百巻の大般若の経本は、百巻ずつ、6つのつづらに納められ3頭の馬に揺られて大八田道を長坂上条の龍岸寺へと帰っていった。朝、経本を持ちに行く時には、あばれまくって馬方をてこずらせた春馬も、この時はおとなしく主人に従って歩いて行った。
こんな祭りも、太平洋戦争がはじまった昭和16年頃を最後に行われなくなってしまった。
平成11年3月28目、春祭りの日。観音堂に集まったのは、20人ほどの区の役員と祭り当番だけだった。 龍岸寺の方丈さんが一人、台の上に一巻だけ置かれた経本を手に、お経を唱えながらあのしぐさを繰り返した。祭典のあと、会場を公民館に移し、そこに集まった子供から高齢者までの区民は、方丈さんの法話と懐かしい「昔の春祭り」の話を聞いた。 (板山長治)
長坂町教育委員会(平成12年)「長坂のむかし話」 長坂町役場
このデザインソースに関連する場所
Old Tale
Archives
物語
山梨各地に伝わる昔話や伝説、言い伝えを収録しています。昔話等の舞台となった地域や場所、物品が特定できたものは取材によって現在の状態を撮影し、その画像も紹介しています。


















